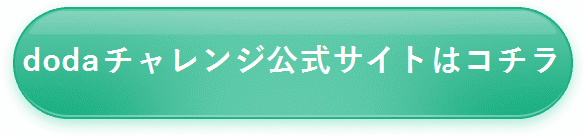dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します

dodaチャレンジを利用しようと思ったのに「断られた」という声を耳にすると、不安に感じる方もいるかもしれません。
でも安心してください。
断られたように見えるケースにも、きちんとした理由や背景があります。
dodaチャレンジは、障がいのある方の就職・転職を支援するためのサービスですが、すべての方に無条件で求人紹介ができるわけではありません。
紹介可能な求人とのマッチングや、サービスの提供対象に当てはまるかどうかを丁寧に確認したうえでの判断があるからです。
この記事では、dodaチャレンジで求人紹介を断られる可能性があるケースについて、よくある理由や特徴をもとにわかりやすく解説していきます。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、利用者一人ひとりの希望にできるだけ寄り添いながら求人を紹介していますが、紹介可能な求人が見つからないこともあります。
これは、その方の希望条件と求人市場とのバランスによって起こることで、サービスの質が悪いというわけではありません。
特に希望が厳しすぎる、または特定の職種・エリアに限定されすぎている場合、マッチする求人が見つけづらくなることがあります。
その結果、「今回はご紹介できる案件がありません」と案内されることがあります。
これは一時的な状況である場合もあるため、条件を緩和したり、タイミングを見直したりすることで再度紹介を受けられる可能性もあります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
最近では在宅勤務やフルフレックス制度を導入する企業も増えてきましたが、障がい者雇用枠においてはまだまだ限られた条件での募集が多いのが現実です。
そのため、「完全在宅勤務」「フルリモートのみ希望」「年収500万円以上」といった高い条件を提示すると、紹介可能な求人が非常に少なくなってしまいます。
もちろん希望を持つことは大切ですが、条件を少し緩めて検討することで、新たな選択肢が見えてくる場合もあります。
自分にとって大事な優先順位を整理し、どの条件は譲れてどこは譲れないのかをアドバイザーと一緒に考えることで、紹介の可能性が広がることもあります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
自分のスキルや興味を活かした職種に就きたいという思いは自然なことですが、希望する業種や職種が非常に専門的であったり、採用枠が少ないジャンルである場合は、求人紹介が難しくなることがあります。
たとえば、デザイン職やアート系、編集・ライターといったクリエイティブ職は、障がい者雇用枠での募集が少ない分野に該当します。
これが理由で「紹介できる求人がない」と判断されることもあります。
ただし、今はない求人でも、将来的にチャンスが出てくる場合もあるため、柔軟な姿勢で他の職種にも目を向けておくことが、次の一歩につながるかもしれません。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
希望する勤務地が地方や人口の少ない地域である場合、そもそも障がい者雇用枠での求人自体が少ないこともあります。
dodaチャレンジは全国対応していますが、求人の分布はどうしても都市部に集中しがちです。
そのため、「地元から出たくない」「通勤時間は30分以内に限る」といった条件があると、マッチングできる案件が見つかりにくくなります。
可能であれば、通勤範囲を広げる、あるいは一部リモート勤務を許容するなど、柔軟な条件に調整することで紹介の可能性を高めることができます。
アドバイザーと相談しながら、自分に合う通勤スタイルを探していくのがおすすめです。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、サービスの特性上、一定の条件に該当しない方には支援が難しいと判断される場合があります。
これは差別や選別ではなく、サービスの枠組みとしてサポート可能な範囲があるためです。
たとえば、障がい者雇用枠での求人を紹介するためには、原則として「障がい者手帳」を所持していることが前提とされています。
また、長期間のブランクがあり、社会復帰への段階的な支援が必要な場合には、別の支援機関(就労移行支援など)を案内されるケースもあります。
こうした判断は、その人の将来を考えて適切なサポートにつなげるための措置でもあるので、必要に応じて他の選択肢も検討することが大切です。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジで紹介される求人のほとんどは、「障がい者雇用枠」での募集です。
そのため、障がい者手帳を持っていない方には、制度上の制限により紹介が難しくなることがあります。
中には「手帳を持っていないけれど配慮は必要」という方もいますが、企業側が採用条件として手帳の所持を求めていることが多く、紹介自体ができないという結果になることもあります。
これはdodaチャレンジに限らず、他の障がい者就職支援サービスでも同様の対応がとられるケースが多いです。
まずは医師と相談し、手帳取得の可否を確認することが、次のステップに進むための第一歩となります。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
長期間仕事から離れていた方や、これまでに就業経験がほとんどない場合、求人の紹介が難しくなることがあります。
これは、企業側が即戦力やある程度の業務スキルを求めていることが多いためです。
もちろん、すべての求人が高い経験を求めているわけではありませんが、職種や業種によっては一定の実務経験が前提となっているケースもあります。
そのような場合、dodaチャレンジでは、まずは就労移行支援事業所の利用を検討するよう提案されることもあります。
段階的に就労スキルを身につけることで、将来的に転職活動がスムーズになるため、焦らずに基礎から取り組む姿勢が大切です。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
現在の体調や精神的な状態によっては、「まずは無理をせずに安定することを優先しましょう」という判断がなされることもあります。
dodaチャレンジは就職支援サービスであり、継続的な勤務が可能な状態であることが前提となっています。
そのため、就労が現時点で難しいと見られた場合には、より適切な支援を受けられる「就労移行支援事業所」などを紹介してくれることがあります。
これは決して否定ではなく、その人の将来の安定就労に向けた一歩としての提案です。
自分に合ったタイミングで無理なく進めるための支援体制が整っていることは、dodaチャレンジの信頼できるポイントでもあります。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジでは、面談の内容をもとに適切な求人が紹介されるため、準備不足や印象面が原因で紹介を受けにくくなることがあります。
特に、自分の障がいの特性や希望する働き方についてきちんと説明できない場合、アドバイザーも適切な提案がしづらくなってしまいます。
また、どんな職種で働きたいか、将来的にどのようなキャリアを築きたいかといったビジョンが曖昧なままだと、具体的な求人につなげにくくなることもあります。
面談はただのヒアリングではなく、自分を伝える大切な場なので、事前に準備をして臨むことで、希望に近い求人に出会いやすくなります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
アドバイザーとの面談では、障がいの特性や配慮してほしいことをできるだけ明確に伝えることが大切です。
「通院の頻度」「特定の作業で困難を感じる場面」「疲労しやすい時間帯」など、具体的な状況を共有できると、企業に対して適切な提案や交渉が可能になります。
これらの説明が曖昧だったり、「うまく説明できないから話さない」という姿勢だと、紹介できる求人が限られてしまうことがあります。
話すのが苦手でも、事前にメモを用意したり、ポイントを整理しておくだけでも伝わりやすくなるので、面談前の準備はとても重要です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
自分がどんな仕事に興味があるのか、どんな環境で働きたいのかといった希望がぼんやりしていると、求人紹介の幅も狭まってしまいます。
dodaチャレンジでは、スキルや経験に合わせて求人を提案してくれますが、「なんでもいい」「どこでもいい」といった曖昧な回答だと、アドバイザーも判断に迷ってしまうことがあります。
働く上で大切にしたいことや、自分の得意・不得意を明確にしておくことで、より的確なサポートを受けられるようになります。
小さなことでも構わないので、事前に希望を整理しておくと面談がスムーズに進みやすくなります。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの職歴や業務経験がある場合、その内容をわかりやすく伝えることも大切です。
自分にとっては当たり前だった仕事内容でも、アドバイザーにとっては判断材料の一つとなるため、職務内容を明確に説明できるかどうかがポイントになります。
特に、「どんな仕事をどのくらいの期間していたか」「どんなスキルを身につけたか」などを簡潔にまとめておくと、面談でもスムーズに伝えられます。
職務経歴書の作成に不安がある場合でも、事前にアドバイザーに相談できるので、一人で抱え込まずに準備することが大切です。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応をうたっていますが、実際には地域によって求人の数に差があります。
特に北海道・東北・四国・九州などの地方エリアでは、都市部に比べて企業の数が限られており、希望する条件に合う求人が少ないと感じることもあります。
また、完全在宅勤務のみを希望している場合には、選べる求人がさらに絞られてしまいます。
こうした状況はdodaチャレンジに限ったものではなく、全国的な障がい者雇用の課題でもあります。
とはいえ、オンライン対応やフルリモートの案件も少しずつ増えてきているため、選択肢が広がる可能性もあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方エリアに住んでいると、就職活動で不利になるのではと感じることがあるかもしれません。
dodaチャレンジでは全国対応をしており、オンラインで面談や相談ができる環境が整っていますが、それでも都市部と比べると求人の数には差があるのが現実です。
特に地方では、障がい者雇用を積極的に行っている企業が限られていたり、在宅勤務制度が導入されていない企業も少なくありません。
そのため、「希望する条件に合う求人が見つからなかった」という声が出ることもあります。
こうした場合でも、アドバイザーと一緒に条件を見直すことで、新たな選択肢が見えてくる可能性もあります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
最近は在宅勤務のニーズが高まっており、障がいのある方にとっても働きやすい選択肢の一つとなっています。
しかし、完全在宅勤務に限定して仕事を探す場合、求人数がかなり限られてしまうことがあります。
dodaチャレンジでも在宅勤務可能な求人は扱っていますが、地域によっては選べる案件が少ないため、「条件を広げないと紹介が難しい」とアドバイザーから提案されることもあります。
できるだけ希望条件を柔軟にしつつ、自分の優先順位を明確にすることで、より多くの選択肢を得られる可能性が高まります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、利用者との信頼関係を大切にしているため、登録情報に不備や虚偽の記載がある場合には、サービスの利用を断られてしまうことがあります。
特に、障がいの有無や就労可能な状況についての情報は、求人のマッチングに直接影響する重要な項目です。
そのため、正しい情報をもとに支援を行う必要があり、不正確な内容で登録されると、サービス自体が成り立たなくなってしまいます。
たとえば「手帳が未取得なのに取得済みと入力してしまった」「実際は働ける状況にないのに就労可能と記載した」など、悪気がなくても誤解を生むことがあるので注意が必要です。
登録時は、自分の状況を正直に記載することが、結果的に自分に合った支援を受ける第一歩になります。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
dodaチャレンジは、基本的に障がい者手帳を所持している方を対象にした支援サービスです。
そのため、手帳が未取得のまま「取得済み」として登録をしてしまうと、後から確認が取れた際に、サービスの継続が難しくなる場合があります。
中には「すぐに手帳を申請予定だった」「取得見込みがあるから」といった理由で誤って入力してしまう方もいますが、実際の運用では正確な情報が求められるため、意図的でなくても利用不可となることがあります。
もし未取得の段階でも相談をしたい場合は、正直にその旨を伝えた上で、事前相談という形で受け入れてもらえるか確認するのが安心です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
dodaチャレンジは「就労可能な状態にある方」を対象とした就職・転職支援サービスのため、医師からの就労制限がある場合や、体調的に働くのが難しいタイミングでは、登録を見送られることがあります。
たとえば、「早く働かないといけない」と焦って無理に登録してしまったとしても、面談の中で状況を確認した結果、「今は休養が必要です」と判断されるケースも少なくありません。
dodaチャレンジでは、無理をして働くことを推奨するわけではなく、長く安心して働けることを大切にしているため、就労に不安がある方は、まずは体調を整えてから登録するのがおすすめです。
職歴や経歴に偽りがある場合
職歴や経歴に偽りがあると、サービス利用中に紹介される求人とのマッチングに大きな影響を与えてしまいます。
たとえば「実際には経験がない業務を経験ありと申告した」「ブランク期間を隠して記載した」など、ほんの少しの誤魔化しであっても、企業との信頼関係にヒビが入る原因になります。
dodaチャレンジでは、求職者と企業双方が安心してやり取りできるように、正確な情報の提供を前提としています。
そのため、万が一虚偽の申告が判明した場合は、サポートが中断される可能性もあるのです。
自分に合った職場に出会うためにも、正直な情報をもとに相談を進めることがとても大切です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジの選考プロセスでは、キャリアアドバイザーによるサポートが充実していますが、最終的な合否は求人を出している企業によって決まります。
そのため、応募後に不採用となった場合、「dodaチャレンジに断られた」と感じてしまう方もいますが、実際には企業側の選考基準や社内事情による判断が大半です。
希望する求人に落ちてしまったからといって、自分が否定されたように感じる必要はありません。
dodaチャレンジでは、一度不採用になっても別の求人を提案してもらえる仕組みが整っているため、ひとつの結果にこだわりすぎず、前向きに活動を続けることが大切です。
不採用は企業の選考基準によるもの
応募先の企業で不採用となった場合、それは企業の選考基準や社内のポジション事情によるものであり、必ずしもあなた自身に問題があったわけではありません。
たとえば、他によりスキルが近い応募者がいたり、企業の採用枠が急遽変更されたというケースもあります。
dodaチャレンジでは、面接対策やフィードバックも行ってくれるため、不採用の結果を次に活かすサポートも充実しています。
「なぜ落ちたのか」よりも「次にどこで自分を活かせるか」に目を向けることで、より自分に合った職場に出会える可能性が高まります。
選考はあくまでもご縁なので、落ち込まずに次へ進んでいくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジを利用しようとした際に「求人の紹介が難しいです」と断られてしまった場合、「自分はもう働けないのでは」と不安になってしまうこともあるかもしれません。
でも大丈夫です。
実は、そのような状況から一歩ずつキャリアを積み重ね、再チャレンジで内定を獲得した方もたくさんいらっしゃいます。
求人紹介を断られた背景には、「今のタイミングではマッチする求人がない」「もう少しスキルや職歴を補った方が良い」といった理由があることが多く、そうした課題を補うための方法はしっかりと用意されています。
この章では、断られてしまった時に焦らず前向きに行動を起こすための具体的な対処法を、状況ごとに分けて詳しくご紹介していきます。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
これまでの職歴が短かったり、アルバイト中心の経験しかない場合、「正社員での雇用は難しいのでは」と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、スキルや職歴は後から身につけることができるものです。
dodaチャレンジで求人紹介を受けられなかったとしても、今後のために準備を整えておくことで、再チャレンジの際にはより有利な立場で転職活動に臨めるようになります。
ポイントは、今すぐに大きな実績を求めるのではなく、自分のペースで少しずつ実力をつけていくことです。
以下では、スキル不足・職歴不足を感じたときに取り組める有効な方法をいくつかご紹介します。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
スキルに自信がないと感じる方には、ハローワークが実施している職業訓練を活用するのがおすすめです。
特にパソコン操作に不安がある場合、WordやExcel、データ入力など、就職活動で役立つスキルを基礎から学ぶことができるコースが多く用意されています。
これらの講座は無料または低額で受講できる場合がほとんどで、経済的負担も少なく済みます。
修了証や受講歴は履歴書にも記載できるため、採用担当者に対して「学ぶ意欲がある」「スキル習得に前向きである」という印象を与えることができます。
再度dodaチャレンジに登録する際のアピール材料にもつながるので、積極的に検討してみてください。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
職歴やスキルに不安がある場合は、就労移行支援の利用も非常に有効です。
就労移行支援では、実際の職場を想定した訓練を通して、ビジネスマナーやPC操作、報告・連絡・相談の練習などを行うことができます。
さらに、メンタルサポートや体調管理の支援も受けられるため、働き続けるための土台づくりとして非常に心強い存在です。
継続的に通うことで生活リズムが整い、就労準備が整った段階でdodaチャレンジなどの転職支援サービスを再活用する方も多くいます。
「いきなり働くのは不安」という方にもおすすめできる選択肢です。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格は、自分のスキルを客観的に証明できる大きな武器になります。
とくに、障がい者雇用枠で人気がある事務職や経理職では、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級などの資格を持っていると評価されやすく、求人紹介の幅が大きく広がる可能性があります。
通信講座や独学で取得できる資格も多く、短期間でチャレンジできるのもメリットです。
スキルアップをしながら自信をつけたい方は、資格取得に取り組むことで、再チャレンジ時により強力なアピールポイントを持つことができるようになります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養機関があるなど)の対処法について
ブランク期間が長くなると、「いまさら働けるのかな」「面接でどう説明すればいいんだろう」といった不安を抱える方も多いと思います。
ですが、ブランクがあること自体は決して悪いことではありません。
大切なのは、その期間を経て「今は働きたいと思っている」という気持ちがあるかどうかです。
dodaチャレンジでは、安定した就労を前提とした支援が行われているため、タイミングや状況によっては就労移行支援など別のサービスを案内されることもあります。
ここでは、ブランクがある方が少しずつステップを踏みながら社会復帰を目指すための具体的な対処法をご紹介します。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
長いブランクがある方には、まずは生活リズムを整えながら無理のない形で働く準備をすることが大切です。
その際に役立つのが就労移行支援事業所です。
毎日決まった時間に通所することで、規則正しい生活を取り戻し、徐々に働く体力や集中力を養うことができます。
さらに、就労訓練を通して小さな「成功体験」を積むことができ、自信にもつながっていきます。
このような実績は再びdodaチャレンジなどの支援サービスを利用する際にも大きなアピール材料になりますので、焦らず丁寧にステップを踏むことが成功への近道です。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイム勤務に戻るのが不安な場合は、週1〜2日から始められる短時間のバイトや在宅ワークに挑戦してみるのも一つの方法です。
小さな仕事でも継続的に働けた実績があることで、次の就職活動の際に「勤務が継続できる」という証明になります。
また、面接でブランクの理由を説明する際にも、「体調に配慮しながら徐々に働く訓練をしてきた」という内容がプラスに働くことがあります。
仕事の内容よりも、安定して続けられることを重視して取り組むことが大切です。
まずは自分のペースで一歩を踏み出してみることから始めましょう。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
ブランクが長い方や、職場での経験を増やしたいと考えている方には、企業実習やトライアル雇用への参加もおすすめです。
これらの制度は、一定期間職場で働きながらスキルや適性を見極める機会として活用されており、実際に雇用につながるケースも少なくありません。
何よりも、実際の業務を通して得た経験は、履歴書や職務経歴書に書ける「実績」となり、再びdodaチャレンジを利用する際にも大きな強みになります。
実習先での評価が高ければ、そのまま採用される可能性もあるため、自信をつけるためにも非常に有効なステップです。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいると、「通える範囲に求人がない」「フルリモート希望だけど求人が見つからない」といった悩みが出てくることがあります。
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、地域によって求人の数や種類にはどうしても差があるため、紹介が難しい場合もあります。
そんなときは、一つのサービスにこだわらず、視野を広げて複数の方法を併用していくことが大切です。
働き方や目指すキャリアによって、今できること・すぐに始められることは意外と多くあります。
焦らず、でも諦めずに少しずつ前に進むことで、新しい可能性が見えてくることもあります。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジで求人が見つからなかった場合は、他の障がい者専門エージェントも検討してみるのがおすすめです。
たとえば、在宅勤務に特化した「atGP在宅ワーク」や、就職支援と訓練を組み合わせた「ミラトレ」、企業と求職者のマッチングに強みを持つ「サーナ」など、それぞれに特色があります。
エージェントごとに取り扱う求人が異なるため、複数登録しておくことで、より自分に合った求人に出会えるチャンスが広がります。
特に在宅勤務OKの求人を希望している方には、こうした併用の工夫が有効な手段になると思います。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
求人が見つからないときでも、自宅でできる仕事を通じて「実績」を作ることは可能です。
最近では、クラウドソーシングサービスを活用して、ライティングやデータ入力、軽作業といった案件に取り組む人も増えています。
ランサーズやクラウドワークスなどのサービスでは、自分のスキルやペースに合わせて仕事を選べるため、就職活動と並行して経験を積むことができます。
こうした取り組みは、「何もしていない空白期間」を避けるだけでなく、自分の働き方のスタイルを見つけるヒントにもなります。
継続して取り組めば、自信にもつながっていきます。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
dodaチャレンジのような大手エージェントではカバーしきれない地域密着型の情報を得るには、地元の障がい者就労支援センターやハローワークの活用も効果的です。
地方の中小企業や自治体の採用情報など、地域に根ざした求人を扱っていることもあります。
特に、ハローワークでは障がい者雇用に積極的な企業との連携も進められており、通勤可能な距離で働ける職場を見つける手助けをしてくれます。
就職支援員との面談を通じて、働き方の相談や職場体験の機会を得られる場合もあるので、地域の支援機関をうまく活用していくことが大切です。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
希望条件が多すぎると、求人の選択肢が狭まり、結果として「紹介が難しいです」と言われることがあります。
たとえば、「完全在宅勤務」「週3日勤務」「年収◯万円以上」といった条件をすべて満たす求人は、どうしても限られてしまいます。
とはいえ、無理に妥協するのではなく、希望を整理して「今はここを優先する」「将来的にこの働き方を目指す」といった段階的な考え方に切り替えることで、現実的な転職活動がしやすくなります。
アドバイザーと相談しながら、柔軟に条件を見直していくことが、より良い就職への第一歩になるはずです。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
希望条件が多くなりすぎている場合には、「絶対に譲れない条件」と「可能なら叶えたい希望」をはっきりと分けて整理することが大切です。
たとえば、「体調的に在宅は必須」「週3日が限界」といった項目は最優先としつつ、「年収は将来的に上げていければOK」といった柔軟性を持たせるだけでも、紹介できる求人の幅が広がる可能性があります。
アドバイザーも優先度が分かることで、より的確な提案がしやすくなるため、希望を一度紙に書き出して整理するのも効果的です。
自分の中で基準をはっきりさせることで、納得のいく選択がしやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
もし「条件が厳しすぎて紹介できる求人がない」と言われた場合でも、すべてを一気に緩める必要はありません。
譲歩できる項目だけを見直して、アドバイザーに再提示するだけでも大きな前進になります。
たとえば、「出社は週1日までならOK」「フルタイムは厳しいが週4日なら可能」など、少しの調整で紹介できる求人が出てくることもあります。
自分の体調やライフスタイルと相談しながら、「ここまでなら譲れる」というラインを明確にすることで、アドバイザーも改めてマッチする求人を探しやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
理想の働き方をすぐに実現するのが難しい場合は、段階的にキャリアアップしていく戦略も有効です。
まずは現在のスキルや体調に合わせてスタートできる働き方を選び、そこから経験を積んで少しずつ条件を広げていく方法です。
たとえば、「最初は短時間勤務でスタートし、半年後にフルタイムへ」「一般事務から始めて将来的に専門職へ」というように、目標を中長期で見据えることで、焦らずに自分らしいキャリアを築いていけます。
スモールステップで進めていくことで、無理なく理想に近づけるという安心感も得られます。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジでは、基本的に障がい者手帳を取得している方を対象に支援が行われているため、まだ手帳を持っていない方や取得が難しい状況にある方は、登録を断られてしまうことがあります。
ただし、これは「就職の可能性が閉ざされる」という意味ではありません。
現在の状況に応じて、他の選択肢を検討することで、将来のためにできることはたくさんあります。
たとえば、手帳取得の準備を進めたり、別の支援機関を活用するなど、段階的にステップを踏むことが大切です。
焦らずに自分の状態と向き合いながら、適切な支援につながる方法を見つけていくことが、今後の安定した就労に繋がっていきます。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいを抱えている方の中には、「手帳をもらえるか分からない」「どこに相談すればいいか分からない」と悩んでいる方も少なくありません。
実際には、主治医に診断書の作成を依頼し、市区町村の窓口に申請することで、手帳の取得が可能なケースがあります。
診断名や状態によっては、一定の条件を満たすことで、精神障がい者保健福祉手帳などの取得対象となることがあります。
まずは医師に相談し、自分の症状がどのように評価されるのかを確認することが第一歩です。
また、自治体によっては相談支援専門員が在籍している場合もあるため、不安な点があれば窓口での相談もおすすめです。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳の取得がまだであったり、取得が難航している場合には、就労移行支援事業所やハローワークでのサポートを活用する方法があります。
中には、障がい者手帳がなくても応募できる求人や、「一般枠」として就職活動を進める道もあります。
就労移行支援では、生活リズムを整えながら働くための準備ができるだけでなく、必要なスキルや社会経験を積むこともできます。
就労経験を重ねたうえで、将来的に手帳を取得したり、体調が安定した時期に再度dodaチャレンジに相談するという流れも自然な選択肢です。
今できることから一つずつ取り組むことで、焦らずに前進することができます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
体調が安定していなかったり、今は働ける自信が持てないと感じている方は、まず治療やリハビリ、生活の安定を優先することが大切です。
dodaチャレンジのサポートは、長く安心して働き続けることを前提としているため、無理をして登録しても十分な支援が受けられない可能性があります。
主治医と相談しながら、自分のペースで通院や療養に集中し、必要なタイミングで手帳取得の準備を進めることがおすすめです。
体調が整い、働ける状況になった時に、改めてdodaチャレンジに相談することで、自分に合った職場を紹介してもらえるチャンスが広がります。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジに登録できなかった場合でも、他にもさまざまな就労支援サービスがあります。
たとえば、ハローワークの障がい者専門窓口では、手帳の有無にかかわらず相談に乗ってくれることがあります。
また、地域の障がい者就業・生活支援センターや、NPO法人が運営している就労支援プログラムなども存在します。
さらに、就労移行支援事業所では、就職に必要なスキルを身につけながら、働く自信を取り戻すサポートが受けられます。
それぞれの機関によって得意な支援の内容が異なるため、自分の状況や目標に合った場所を選ぶことが重要です。
dodaチャレンジにこだわらず、他の選択肢を積極的に探していくことで、結果的に自分に合った職場に出会える可能性が高まります。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジを利用しようとした際、「精神障害や発達障害があると紹介を断られることがあるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、dodaチャレンジは精神障害・発達障害・身体障害など、すべての障がいに対応する専門的な支援体制を整えており、配慮が必要な方に対しても親身にサポートを提供しています。
ただし、障がいの特性や現在の就労可能な状態によっては、タイミングや希望条件によって紹介が難しい場合もあります。
本章では、特に身体障害者手帳を持っている方の就職事情に焦点をあてながら、採用されやすい傾向や注意点などを詳しくご紹介していきます。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持っている方の就職は、障がいの種類や等級によって状況が大きく異なります。
一般的に、身体障がいの方は障がいの内容が視覚的にわかりやすいことが多いため、企業側も職場での配慮を具体的にイメージしやすく、採用に前向きなケースが多いとされています。
また、通勤や作業に支障が出にくい範囲での障がいであれば、一般事務などの職種にもチャレンジしやすく、選べる求人の幅も比較的広い傾向があります。
ただし、身体の部位や程度によっては制限もあるため、自分に合った働き方を理解しながら、アドバイザーと一緒に進めていくことが大切です。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳の等級が比較的軽度である場合、企業にとっての業務上の配慮が最小限で済むことから、採用されやすい傾向があります。
例えば、移動時に少し時間がかかる程度であれば、他の業務に影響を与えることが少なく、職場における合理的配慮も比較的簡単に整えることができます。
そのため、等級が低い方は一般職としての採用も視野に入れられる場合が多く、職種の選択肢も広がります。
実際に、等級が軽度であっても障がい者雇用枠を利用し、職場環境に配慮された中で長く働く方も増えています。
dodaチャレンジでも、個々の状態に応じた提案がされるため、まずは相談してみることが大切です。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいの多くは視覚的に分かりやすく、企業側が「どのような配慮が必要か」を把握しやすい特徴があります。
そのため、採用時のミスマッチが起きにくく、安心して受け入れられる傾向があるのです。
「見えない障がい」と違い、業務上の配慮ポイントが明確になりやすいため、企業としても働き方の調整がしやすくなります。
例えば、通勤時の配慮や、作業内容の調整などを事前に話し合っておくことで、双方にとって納得のいく就労環境が整います。
こうした理由から、身体障がいをお持ちの方は比較的スムーズに就職活動が進みやすいといえます。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がいのある方への配慮は、具体的な対応策が明確であることが多く、企業側としても準備がしやすいです。
たとえば、建物のバリアフリー化や車椅子利用者のための導線整備、階段や段差への対応、デスクの高さ調整など、施設面の対策が中心になります。
また、業務内容の制限についても「重い荷物を持たせない」「長時間の立ち仕事を避ける」など、配慮すべきポイントが比較的はっきりしているため、採用判断がしやすいという側面があります。
こうした背景から、企業にとっても「受け入れやすい障がい」と認識されることが多く、採用につながりやすくなっています。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
身体障がいの内容によっては、通勤や日常業務に支障が出ることもあり、その場合は紹介される求人が限られてしまう可能性があります。
たとえば、上肢に障がいがある場合はキーボード操作が困難になりやすく、下肢に障がいがある場合は通勤や移動が大きな負担になることもあります。
そのため、在宅勤務やリモート対応が可能な求人、通勤負担が少ないエリアの職場など、条件が絞られることになります。
ただし、dodaチャレンジではこうした制約にも対応できる求人の紹介を行っているため、自分に合った働き方を模索しながら進めることが可能です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体的な障がいがあっても、日常的なコミュニケーションに問題がない場合には、一般職種への採用が進みやすい傾向があります。
企業側が特に重視するのは、報告・連絡・相談がスムーズにできるかどうか、職場での人間関係に支障がないかといった点です。
そのため、対面での会話や電話対応、メールでの連絡が問題なく行える場合には、事務職をはじめとした多くの職種に挑戦するチャンスがあります。
自分の得意なコミュニケーション手段をアピールすることで、採用に近づくケースも少なくありません。
苦手な点よりも、できることを丁寧に伝える姿勢が大切です。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいを持つ方にとって、通勤や業務の負担が比較的少ないPC業務や事務職は、求人が多い分野のひとつです。
ExcelやWordを使ったデータ入力、書類作成、電話対応などが主な業務内容となり、座り仕事が中心となるため、身体への負担が少なく安心して取り組めるという声も多いです。
PCスキルに自信がある方や、事務経験がある方にとっては、特にチャンスの広がりやすい職種といえます。
また、最近では在宅勤務や時短勤務の相談が可能な求人も増えてきているため、無理のない働き方を実現したい方にとっても選択肢が豊富になっています。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持っている方の就職活動には、独特の課題と配慮が必要とされることが多いです。
うつ病、双極性障がい、統合失調症、不安障がいなど、さまざまな疾患が対象になりますが、いずれも「見えにくい障がい」であることから、企業側にとっては理解が難しく、不安を感じやすい部分でもあります。
そのため、就職においては「症状の安定性」や「職場での継続的な勤務が可能かどうか」といった点が非常に重視されます。
支援機関やエージェントを通じて、しっかりと情報を整理し、自分の状態を適切に伝えることが、安心して働ける職場に出会うための第一歩になります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいのある方が就職活動をするうえで、企業側が最も気にするのは「症状が安定していて、継続して勤務できるかどうか」という点です。
過去に長期離職や頻繁な転職があった場合でも、直近の生活状況や治療状況が安定していれば、前向きに評価されることもあります。
安定して通勤できるリズムや、仕事に取り組めるコンディションを整えておくことで、企業側も安心して受け入れやすくなります。
日々の生活習慣や通院状況についても整理し、アドバイザーとの面談や面接の場でしっかり伝えることが、良い結果につながりやすくなるポイントです。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは外見からは分かりにくく、企業にとっても「どのような配慮が必要か」「働き始めたあとに困ることがあるのか」など、明確にイメージできないケースが多いです。
そのため、採用担当者の中には、精神障がいを持つ方の受け入れに慎重になってしまう場合もあります。
そうした不安を取り除くためにも、事前に症状の傾向や配慮が必要なポイント、就労経験の有無などを整理しておき、具体的に説明できる準備がとても大切です。
企業側の理解を深めるきっかけにもなり、自分に合った職場とマッチングしやすくなります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
採用面接では、配慮事項の伝え方が就職活動の成否に大きく関わってきます。
「こんなことを伝えたら不利になるかも」と感じてしまい、遠慮して伝えないままでいると、入社後にギャップが生まれて働きづらくなることもあります。
たとえば、「集中力が続きにくい時間帯がある」「業務の優先順位を明確にしてほしい」といった内容は、事前に伝えておくことで、企業側も対応しやすくなります。
無理なく働き続けるためには、あらかじめ正直に伝えたうえで、それに理解を示してくれる企業を選ぶことが何より大切です。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳を所持している方の就職は、障がいの程度や支援体制によって選択肢が大きく異なります。
療育手帳は自治体によって名称や区分が異なりますが、基本的にはA判定(重度)とB判定(中軽度)に分かれており、それぞれで就職先の幅も変わってきます。
A判定の方は福祉的な就労支援を活用するケースが多く、B判定の方は一般企業での就労も現実的な選択肢として検討されることがあります。
いずれの場合も、自分の得意・不得意を理解し、それに合った職場環境を選ぶことが安定した就労につながります。
支援機関のサポートも上手に活用しながら、段階的にステップアップを目指す姿勢が大切です。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳を持っている方の就労支援では、A判定かB判定かによって支援内容や就職先の選び方に違いが出てきます。
A判定の方は、一般就労が難しいとされるケースが多いため、福祉的な支援を受けながら働くスタイルが主流になります。
一方で、B判定の方は、軽度の知的障がいに該当することが多く、一般企業での雇用も現実的です。
この区分は就職活動の進め方にも影響を与えるため、支援機関やエージェントと相談しながら、自分に合った働き方を一緒に見つけていくことが大切です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)と診断されている方の場合、一般企業での就職はハードルが高く感じられることもあります。
そのため、福祉的な支援を受けられる「就労継続支援B型」や「就労移行支援」を活用して、まずは作業の習慣づけや社会性のトレーニングを積むところからスタートするケースが多いです。
これらの支援では、無理のないペースでの作業や、支援スタッフによる手厚いフォローが受けられるため、働くことへの不安を少しずつ減らしながらステップアップを目指せます。
焦らずに、自分のペースで「働く力」を育てていくことが大切です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)を持つ方の場合は、一般企業での就職も視野に入りやすくなります。
特に、サポート体制が整っている企業や、障がい者雇用に積極的な職場では、実際に多くの方が活躍しています。
この判定では、ある程度の業務遂行力やコミュニケーション能力が備わっていることが多いため、就労移行支援などを活用しながら職場体験を積むことも効果的です。
また、面接時には得意なこと・不得意なことを明確に伝え、自分に合った業務を相談できることも、スムーズな就職につながるポイントになります。
無理せず、少しずつ自信を積み重ねていくことが成功のカギです。
障害の種類と就職難易度について
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
就職や転職を考える際、「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかは、障がいのある方にとって大きな選択となります。
それぞれの雇用枠には特徴や採用の前提条件が異なり、自分に合った働き方を考えるうえで理解しておくことがとても大切です。
障害者雇用枠では、障がいのある方が安心して働けるような配慮が前提とされているのに対し、一般雇用枠では他の応募者と同じ基準で評価される傾向があります。
それぞれにメリットや課題があるため、自分の体調や就労環境の希望に合わせて、どちらの枠が適しているかを検討することが重要です。
ここでは、それぞれの雇用枠の特徴について具体的にご紹介します。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠とは、企業が障害者雇用促進法に基づいて設けている採用枠のことです。
これは、障がいのある方が働きやすい環境を整えるために用意されたもので、企業には障がい者を一定数以上雇用する義務が課されています。
この枠では、障がいの内容や特性に応じて必要な配慮を受けながら働くことができるため、無理なく自分のペースで仕事に取り組みたい方にとって非常に心強い選択肢です。
企業側もあらかじめこの雇用枠の存在を理解しているため、受け入れ態勢が整っている場合が多く、安心して働ける環境が期待できます。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
2024年4月から、障害者雇用促進法に基づき、民間企業に課される障がい者の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。
このルールにより、従業員数が一定規模以上の企業は、障がい者を雇用する義務があり、未達成の場合は納付金が発生することもあります。
そのため、多くの企業が障害者雇用に前向きに取り組むようになっており、専用の雇用枠や配慮された業務内容、職場環境の整備が進められています。
この制度により、障がいのある方が社会の中で活躍しやすくなり、選択肢も広がってきているのが現状です。
法律に支えられた雇用の仕組みだからこそ、安心して応募できるというメリットがあります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠での就職では、障がいの有無を最初からオープンにしたうえで応募を行い、企業にはどのような配慮が必要かを明確に伝えることが基本となります。
たとえば、体力面での制限や勤務時間の調整、定期的な通院が必要な場合など、具体的な配慮事項を事前に共有することで、企業側も働きやすい環境を整えやすくなります。
このプロセスによって、入社後に「話が違った」と感じることが少なくなり、安心して仕事に集中することができます。
自分の状況を正しく伝えることで、職場との信頼関係も築きやすくなるのがこの枠の特徴です。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠とは、障がいの有無に関係なく、すべての応募者が同一の基準で選考を受ける採用方式です。
この枠での応募では、企業は障がいがあるかどうかに関わらず、スキルや経験、適性などを基準に採用を判断します。
そのため、障がいのある方にとっては、他の候補者と同じ土俵で競い合う形となり、ハードルが高く感じられることもあります。
ただし、スキルに自信がある場合や、特別な配慮が必要ないという方にとっては、選択肢を広げる手段にもなります。
自分にとってどちらの枠がより良いかを見極めることが、納得できる働き方につながっていきます。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠で応募する場合、障がいの有無を企業に伝えるかどうかは本人の判断に委ねられます。
障がいがあることをあえて開示せずに就職するスタイルを「クローズ就労」と呼び、逆に自己申告する場合は「オープン就労」と呼ばれています。
クローズ就労を選ぶことで、選考での不利を避けられるという面もありますが、入社後に体調や配慮が必要な場面が出てきた場合、理解を得にくいというデメリットもあります。
どちらを選ぶかは、自分の体調や働き方への希望を踏まえて慎重に検討することが大切です。
信頼できる相談窓口と一緒に決めていくのも安心できる方法です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、基本的に障がいに対する配慮や特別な支援措置は設けられていないのが前提となっています。
企業としても、通常の業務遂行が可能な人材を前提に募集を行っていることが多いため、必要な配慮を受けられない可能性があるという点には注意が必要です。
そのため、働くうえで何らかのサポートが必要な方には、この枠はハードルが高くなる場合もあります。
一方で、自分で配慮が不要だと判断できる方や、スキルに自信がある方にとっては、キャリアアップや年収アップの機会が多いことも事実です。
自分にとって無理のない働き方を選ぶために、どの枠で応募するかを慎重に検討することが大切です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がいのある方が就職・転職活動を行う際に、年齢によって採用の難易度が異なるのかは、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
実際には、若年層ほど求人の選択肢が多く、未経験歓迎の案件も豊富にあります。
一方で、年齢が上がるにつれて求められるスキルや職歴のハードルが高くなり、希望通りの転職が難しくなるケースもあるのが実情です。
企業としても、若年層に長く働いてもらいたいという思いがある一方で、年齢が高い方には即戦力や専門性を求める傾向が見られます。
そのため、自身の年代に合わせた転職戦略が必要になってきます。
次に、年代ごとの雇用傾向について具体的に見ていきましょう。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省が公表している障害者雇用状況報告(2023年版)によると、年代別に見ると障がい者雇用の構成比には明確な傾向があります。
20代や30代といった若年層が比較的高い割合を占めており、初めての就職や未経験からのスタートがしやすい環境が整っている一方で、40代以降になると、求職者に対して企業側が求めるスキルや経験の水準が上がる傾向にあります。
特に50代以降では求人そのものの数も減少し、雇用形態も嘱託や短時間勤務といった形に限定されるケースが増えています。
自分の年齢に応じた職探しの方針を考えるうえで、こうした統計データは非常に参考になります。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代から30代の若年層は、障がい者雇用市場の中でも特に求人の数が多く、未経験からチャレンジできる仕事も豊富にあります。
企業側も若い世代に対しては、将来の成長を見越した採用を行う傾向が強いため、社会経験が少ない場合でも「やる気」や「ポテンシャル」を重視してくれる場面が多く見られます。
そのため、履歴書に目立った職歴がなくても、応募に前向きになれる求人と出会えるチャンスがあります。
また、支援機関や就労移行支援事業所と連携して就職を目指すケースも多く、相談しながら安心して準備を進められる環境が整っている点も大きな強みです。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代に差しかかると、転職市場では求職者に対してこれまでの経験や専門性を求められる場面が増えてきます。
特に未経験分野への転職を希望する場合には、企業側も慎重になる傾向があり、「即戦力になれるかどうか」が重視されます。
そのため、これまでの職務経歴や持っているスキルをどのように活かせるかが鍵になります。
一方で、これまでの経験をうまくアピールできれば、年齢に関係なく評価される場面もあり、「40代だから難しい」と決めつけずに、自己分析と事前準備をしっかり行うことでチャンスをつかめる可能性は十分にあります。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以降の就職活動になると、選べる求人が限定されやすくなります。
求人そのものの数が減少傾向にあるうえ、仕事内容も「特定の業務に限定された職種」や「短時間勤務の契約」などに限られるケースが多くなります。
ただし、過去に積み上げた専門的な経験や、特定分野での実績がある場合には、その強みを活かした職場を見つけられることもあります。
自分の得意なこと、長く続けてきた仕事を見直し、それを武器として提示できるように準備しておくと、選考の場でも強みとして伝えやすくなります。
年齢による不安は誰しもあるものですが、戦略次第で十分に活躍できるチャンスはあります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジのような障がい者向けの就職支援サービスには、公式な年齢制限は設けられていません。
そのため、何歳でも登録や相談を行うことは可能です。
ただし、実際のサービス利用者の中心は20代から50代前半が多く、求人の多くもこの年代を対象にしている傾向があります。
60代以降になると、求人自体が少なくなることもあり、紹介される案件が限られる可能性もあります。
そのため、年齢が高くなってからの就職活動には、就職支援エージェントだけに頼るのではなく、他の公的機関も視野に入れた動き方が大切になってきます。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジの利用にあたっては明確な年齢上限が設けられているわけではありませんが、実際にはサポートの中心となる年齢層は50代前半くらいまでです。
企業側の求人ニーズや就労支援の現場の実情を踏まえると、それ以降の年代になると求人が少なくなる傾向があり、支援の選択肢も限られてきます。
ただし、経験やスキルに特化した案件や、企業との関係性を活かしたマッチングなどでチャンスをつかんでいる方もいます。
年齢を理由に諦めるのではなく、自分に合った支援方法をうまく活用することが、成功の鍵となります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢が高くなってからの就職活動では、dodaチャレンジのような民間サービスだけでなく、ハローワークの障がい者専門窓口や、障がい者職業センターなどの公的機関のサポートも活用するのがおすすめです。
これらの機関では、年齢や障がいの状況に応じて個別支援を受けられたり、企業実習や職場体験の場が提供されることもあります。
また、就職後の定着支援にも力を入れているため、長期的に働き続けることを目指している方にとって心強い味方になります。
民間と公的支援を併用することで、それぞれのメリットを活かしながらより多くの選択肢を持てるようになります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジについて、気になっている方も多いことでしょう。
dodaチャレンジは、新しいキャリアにチャレンジしたい方におすすめのサービスです。
そこで、実際にdodaチャレンジを利用された方々からの口コミや評判について、詳しくお伝えいたします。
多くの方がdodaチャレンジを利用されており、その中には新しいキャリアに成功された方もたくさんいます。
一方で、利用者の中にはサポートの質について不満を抱かれる方もいらっしゃいます。
また、求人情報の充実度や転職活動の効率性についての声もあります。
それでは、dodaチャレンジを実際に利用された方々の生の声をお伝えします。
全体的には、キャリアチェンジを成功させた方が多い一方で、サポートの向上が求められる声も挙がっています。
また、転職活動の際に給料や待遇に関する情報が不足しているという指摘もあります。
最後に、dodaチャレンジを検討されている方々へのアドバイスとしては、自身のキャリアに合った転職先を見つけるためには、しっかりとサービスを比較検討し、自分に合った求人を見つけることが重要です。
また、転職活動においては、しっかりとした計画を立て、自分の希望条件を明確にすることが成功のポイントとなります。
以上が、dodaチャレンジに関する口コミや評判をまとめた内容となります。
ご参考にしていただき、新たなキャリアへの一歩を踏み出す際にお役立てください。
関連ページ: dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジの求人で面接を受けた結果、残念ながら不採用のお知らせを受けた場合、気持ちはとても辛いでしょう。
しかし、そんな時こそ落ち着いて次のステップを考えることが大切です。
まずは感謝の気持ちを持ち、フィードバックを受け入れることで自己成長につなげましょう。
また、自己分析をして強みや改善点を再確認し、次回に活かすよう心掛けることが肝要です。
新たなチャレンジを前向きな気持ちで受け入れ、自らの成長に繋げていきましょう。
チャンスは必ず訪れます。
関連ページ: dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談後に連絡がない場合、応募者として不安と疑問をお持ちかもしれません。
面談後に連絡がない理由は様々ですが、その一端をお伝えいたします。
まず、選考プロセスにおいて応募者の方々が多く、 担当者が一人一人の方に十分な対応をするのが難しいことがございます。
そのため、全ての方に即座に個別のご連絡を差し上げることが難しい状況であることをご理解ください。
また、応募者の方々の中から選考を行うにあたり、慎重かつ公平な審査が行われ、その過程で時間を要する場合がございます。
このような理由から、面談後にすぐに連絡がない場合がございますが、恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
お待たせし大変申し訳ございませんが、今後ともdodaチャレンジへのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
関連ページ: dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、正確で詳細な情報を提供いたします。
まず、面談の流れについてです。
面談は、一般的には応募者と採用担当者との対面形式で行われます。
まず最初に、自己紹介がありますので、自身の経歴や志望動機などをお話しいただきます。
その後、応募者の能力や適性、経験などに関する質問が行われることが一般的です。
面談では、過去の経験や行動などを具体的に例示して説明することが重要です。
また、応募者が抱える課題や問題解決能力などについても深く掘り下げられることがあります。
その際には、自らの経験や知識を交えて丁寧に説明することが好ましいでしょう。
次に、面談で聞かれることについてです。
一般的には、自己PRや志望動機、経歴やスキルに関する質問が多く寄せられます。
また、チームでの働き方やコミュニケーション能力なども重視されることがあります。
応募者自身が、自らの強みや成果を的確に伝えることが求められるでしょう。
最後に、準備が十分であることが重要です。
面談当日には、応募者自身が自己分析を行い、自身の強みや弱み、成長点などを把握しておくと良いでしょう。
また、dodaチャレンジに関する情報や企業情報なども把握しておくことが望ましいです。
自信を持って、落ち着いて面接に臨むことが大切です。
面談を通じて、自己をより深く理解し、自身のキャリアを築いていくための一歩として活用してください。
関連ページ: dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方を対象にした就職・転職支援サービスで、特に障がい者雇用枠での就業を希望する方に向けて丁寧なサポートを行っているのが特徴です。
運営元は大手人材会社パーソルグループで、安定した企業との取引実績をもとに非公開求人も多数取り扱っています。
サービス内容は、求人の紹介だけでなく、キャリアカウンセリングや書類添削、模擬面接なども含まれており、はじめての転職活動でも安心して進められるように手厚いフォローが用意されています。
障がいの特性に合わせた働き方の相談や企業への配慮事項の交渉も代行してくれるため、無理のない就職活動ができるサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジでは、障がい者雇用枠の求人を主に取り扱っているため、基本的には「障がい者手帳」を持っていることがサービス利用の前提となっています。
企業側も手帳の有無を採用条件として設定していることが多く、原則として手帳がない場合は求人の紹介が難しくなるケースがほとんどです。
ただし、精神科や心療内科に通院している方で、将来的に手帳取得を検討している方などには、カウンセリングだけ行って今後の方針を相談することができる場合もあります。
まずは手帳の取得について医師に相談するところからスタートし、そのうえで登録できるかどうかを改めて確認するのがおすすめです。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類によってサービス利用が制限されることは基本的にありません。
身体障害、精神障害、発達障害、知的障害など、さまざまな障がいに対応した支援体制が整っています。
ただし、就業可能な状態にあるかどうかがサービス利用の前提となるため、医師から「現時点での就労は難しい」と判断されている場合や、安定した勤務が難しいと判断された場合には、就労移行支援など別の支援サービスを紹介されることがあります。
これは、その方にとって無理のない支援を選ぶための措置ですので、まずは今の状況を正直に伝えたうえで、最適な支援を一緒に考えていくのが大切です。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、公式サイト内のお問い合わせフォームや、登録後に案内されるマイページ上から申請することができます。
また、担当のキャリアアドバイザーに直接メールや電話で退会の意思を伝えることでも対応可能です。
退会理由について詳細な説明を求められることはありませんので、気軽に手続きを進められます。
万が一、再度利用したい場合は再登録も可能ですので、「一時的に就職活動を休止したい」という方でも安心です。
手続きの詳細や不明点がある場合は、公式サイトのFAQを確認するか、担当者に問い合わせてみるのがおすすめです。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、全国どこからでもオンラインまたは電話で受けることが可能です。
対面によるカウンセリングは主に東京・大阪のオフィスが拠点となりますが、遠方にお住まいの方や通院・体調の都合で外出が難しい方には、リモート形式での対応が用意されています。
予約は公式サイトから簡単に行うことができ、事前に伝えたいことや相談したいことがある場合はフォームで入力しておくと、よりスムーズにカウンセリングが進められます。
初めての就職や転職で不安がある方にとっても、気軽にプロのアドバイスを受けられる安心の体制が整っています。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジの登録には厳密な年齢制限は設けられていませんが、一般的には18歳以上で就労を希望している方が対象となっています。
特に多いのは、20代〜50代の障がいのある求職者ですが、それ以上の年齢の方でも状況に応じてサポートを受けることは可能です。
重要なのは年齢よりも「働きたい意思があるかどうか」「企業とマッチングできる条件があるかどうか」といった点になります。
高年齢だからといって登録が断られるわけではないため、まずはカウンセリングを通じて、自分に合った求人があるかどうかを確認してみるとよいです。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、dodaチャレンジのサービスは現在離職中の方でも利用することができます。
むしろ、再就職を目指す段階でこそ活用しやすいサービスのひとつです。
離職している間にどのような仕事が自分に合っているのかを見直したり、履歴書や職務経歴書の準備をしたり、模擬面接を受けて実力をつけたりと、再出発の準備に最適なサポートが受けられます。
アドバイザーは離職理由やブランクの伝え方についても相談にのってくれるので、自信を持って面接に臨む準備ができます。
働きたいという気持ちがあれば、離職中でも問題なく利用できるサービスです。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
基本的にdodaチャレンジは、就労経験のある方向けの転職支援サービスとして設計されているため、新卒学生に特化したサポートは少なめです。
特に、大学や専門学校に在籍中の方が新卒として就活を行う場合には、「就活エージェント」や大学のキャリアセンターの活用がおすすめです。
ただし、障がい者手帳を持ち、すでに卒業間近で就職準備を本格的に始めている方であれば、dodaチャレンジでの支援対象になることもあります。
状況によっては今すぐの登録が難しくても、将来のために事前相談だけ行うことも可能ですので、一度問い合わせてみると安心です。
参照: よくある質問 (dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談 まとめ
今回は、dodaチャレンジでの断られた経験について、その理由や対処法についてまとめてきました。
断られた理由は様々であり、その中には自己啓発やスキルアップのために必要な挑戦であることもあります。
断られた経験を恐れずに受け入れ、その中から成長や学びを見出すことが重要です。
また、断られた際には自己評価を下げずに、ポジティブな姿勢を保つことが大切です。
他者と比較するのではなく、自身の成長を信じて前向きに取り組むことが成功への近道です。
難しいと感じる体験は成長の機会であり、挫折を乗り越えることで自己成長が促進されます。
自分に厳しく接し、困難な状況に立ち向かうことで、自信やスキルが向上し、次なるチャレンジにも前向きに取り組むことができるでしょう。
断られた経験や難しい体験を否定せず、むしろそれらを自己成長の糧と捉えることが重要です。
dodaチャレンジでの断られた経験や難しい体験は、人生において避けられないものです。
しかし、その経験から学びを得て、成長に繋げることができれば、より強い自己を築くことができるでしょう。
挑戦を恐れず、失敗を恐れず、前向きな姿勢を貫くことで、自己実現に近づくことができると信じています。
どんな困難も乗り越えて、自己成長を遂げていきましょう!