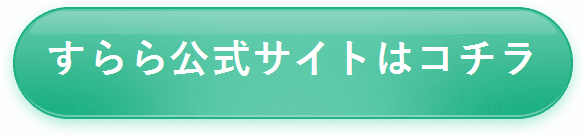すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
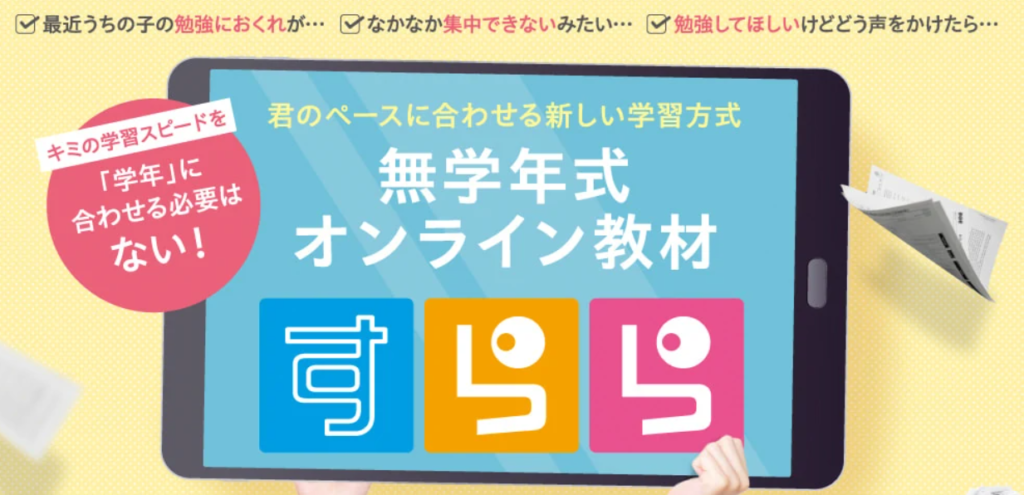
すららは、不登校のお子さんの学習支援に強いタブレット教材として、多くのご家庭に選ばれています。
その中でも特に注目されているのが「すららでの学習が学校の“出席扱い”になることがある」という点です。
文部科学省のガイドラインにより、家庭でのICT教材を活用した学習が「出席」とみなされる可能性があるのですが、それにはいくつかの条件があります。
すららは、その条件をしっかり満たす教材として、全国の教育機関や自治体で採用実績があり、実際に多くの子どもたちが「学校には行けていないけれど、学びは継続できている」と認められています。
不登校の子どもにとってはもちろん、保護者にとっても「出席扱いになるかどうか」は非常に大きな安心材料です。
ここでは、なぜすららが出席扱いとして認められやすいのか、その理由について具体的にご紹介します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららが出席扱いとして認められる最大の理由のひとつは、学習の「質」と「記録」がしっかりと証明できる点にあります。
すららには、学習内容や学習時間、達成度などが自動で記録され、保護者や学校がその記録を客観的に確認できる仕組みが備わっています。
さらに、すららが発行する「学習レポート」は、学校に提出することで「自宅でも継続的な学習をしている」という証明になり、出席扱いの判断材料として評価されることが多いです。
このように、学習のプロセスをきちんと記録・提出できることが、不登校の子どもが学び続けていることの裏付けとなり、学校側の安心感にもつながっているのです。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子どもが日々どのように学習に取り組んでいるかを記録した「学習レポート」が自動で作成されます。
このレポートには、学習した単元や時間、正答率などが詳細に記録されており、学校側が内容を確認することで「確かに学んでいる」という事実を把握することができます。
不登校の場合、「学習していないのでは?」という不安が学校側に生まれることもありますが、すららのレポートを提出することで、その不安を払拭しやすくなります。
これは、ただ教材を与えて終わりではなく、「記録が残る教材」であることが、学校からの信頼にもつながる大きなポイントです。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
保護者が手書きで記録を残すのは、時間も手間もかかりますし、主観的になりがちです。
その点、すららはすべて自動で学習履歴が蓄積されるため、保護者の負担も大幅に軽減されます。
しかも、記録はグラフや数値で見やすく整理されているため、学校の先生にとっても「これなら信用できる」と受け止められやすくなります。
こうした“見える化”の仕組みが、学校との連携や出席扱いの申請をスムーズにしてくれるのです。
親にとっても「証明するものがある」という安心感があり、不登校の状況でもしっかりと学びが継続できているという自信につながります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
出席扱いが認められるためには、「本人に合った学習計画があること」そして「それが継続されていること」が大切です。
すららでは、学習の開始時にすららコーチが子どもの特性や状況をヒアリングし、個別に合わせた学習プランを立ててくれます。
さらに、学習の進み具合に応じてその計画を柔軟に見直しながら継続的にサポートしてくれるため、無理なく学習が続けられる仕組みが整っています。
「計画がある」「計画に沿って学んでいる」というのは、学校に提出する際の説得力にもつながります。
単に教材を使っているだけではなく、計画的に継続して学習しているという点が、出席扱いの判断を後押ししてくれるのです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららでは、すららコーチが一人ひとりの学習状況に合わせて最適なスケジュールを作成してくれます。
これにより、「何を」「いつまでに」「どのように」学ぶかという計画が明確になり、ただ漫然と学習しているわけではないことを学校に説明しやすくなります。
また、すららコーチは月ごとの進捗を確認しながら必要な調整やアドバイスも行ってくれるため、継続的な支援体制が整っています。
これらの情報を保護者が学校に伝えることで、「この家庭では子どもに合わせた学習環境を整えている」と具体的にアピールすることが可能です。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
専任のすららコーチがついてくれることで、学習が三日坊主で終わらずに、長期的に継続されるような仕組みが自然と出来上がります。
家庭の状況や子どもの特性に合わせて無理のない学習計画を提案してくれるため、「やらされる勉強」ではなく「自分のペースで続けられる学び」へと変わっていくのです。
このような伴走支援があるからこそ、保護者も無理なくサポートでき、学校への説明もよりスムーズになります。
学校側も、第三者(コーチ)の視点が入っていることに安心感を持ちやすくなります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは無学年式の教材なので、学年にとらわれず、子どもの理解度に応じた学習ができます。
たとえば「小5だけど、算数は小3の内容から復習したい」「国語は中1レベルに挑戦したい」といったニーズにも柔軟に対応可能です。
この柔軟性があることで、子どもは自分にとって無理のないレベルから学習をスタートでき、着実にステップアップしていくことができます。
これは、出席扱いの審査の際にも「学習の遅れをその子に合わせてカバーできている」点として評価されることが多く、すららが選ばれている理由のひとつです。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららは単なる自宅学習ツールではなく、家庭・学校・教材側の三者が連携して子どもの学びを支える仕組みが整っています。
とくに不登校や通学が難しいお子さんの場合、「学校との連携」が鍵になりますが、すららはその橋渡しの役割をしっかり果たしてくれます。
保護者がどこに相談すればいいか分からない時にも、すららのサポートチームが必要な書類や提出の手順を案内してくれたり、担当のすららコーチが学習記録や報告レポートの作成・提出のフォローをしてくれるなど、実務面での支援も充実しています。
学校側への伝え方が分からないという保護者にとっても、担任や校長との連絡を取りやすくなるようなアドバイスがもらえるのは非常に心強いです。
家庭だけで抱え込まずに、学校と教材側が連携しながら子どもの学習を進められる環境が整っているのは、すららの大きな特長です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
不登校支援の手続きを行う際に、多くの家庭がつまずくのが「どんな書類を用意すればいいのか分からない」という点です。
すららでは、学習証明レポートや出席認定のための書類に関する情報提供をしており、必要な書類の種類や書き方のアドバイス、提出先の確認方法などを丁寧に案内してくれます。
事前に準備すべき内容を保護者が理解しやすいようにまとめた資料も用意されているため、初めての方でも安心して手続きを進めることができます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、学習の進捗や成果を報告するための「学習レポート」について、専用のフォーマットが用意されています。
さらに、すららコーチがこのレポートの記入内容や提出方法について細かくサポートしてくれるため、保護者が一人で悩む必要はありません。
学校に提出する際にも、「どう伝えればよいか」「どの項目を強調すべきか」といった相談にも対応してくれるため、学校側とのコミュニケーションがスムーズに進みます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校のお子さんを持つ保護者にとって、担任や校長とのやり取りはプレッシャーに感じることが多いですが、すららではそのコミュニケーションを円滑に進めるためのサポートも行っています。
学習の様子や到達度をまとめた報告書をすらら側が用意し、必要に応じて「このように説明すると伝わりやすい」といったアドバイスをくれることもあります。
学校側も、明確な学習記録と成果が見えることで、出席認定などの判断がしやすくなるというメリットがあります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が推進する「ICTを活用した教育支援」の取り組みにおいて、不登校の子どもに有効な支援教材として公式に認められた実績を持っています。
そのため、全国の自治体や学校でも導入が進んでおり、学習ツールとしての信頼性は非常に高いです。
こうした公的な評価があることで、学校側も「すららを活用しているなら安心」と受け入れやすくなり、家庭学習を出席扱いとして認定するケースも増えています。
不登校という状況に不安を感じている保護者にとって、国の後押しがあるという事実は大きな安心材料になるはずです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららはこれまでに、全国各地の教育委員会や小中学校との連携実績を多数持っています。
不登校の児童・生徒へのICT教育導入の一環として、自治体単位での採用も進んでおり、「家庭での学習成果を学校評価に反映できる仕組み」が広く浸透しています。
このような実績があるからこそ、学校側も柔軟に対応しやすく、保護者も「すららで学んでいれば大丈夫」と信頼して利用することができるのです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省や各自治体の支援ガイドラインにも掲載されているとおり、すららは公式に「不登校支援教材」として位置づけられています。
この認定は、単に「オンラインで学べる」こと以上に、子どもの多様な発達特性に対応した設計や、継続的な学習記録の保存、保護者や学校との連携体制といった、総合的な学習支援体制が評価されている証です。
実際に、出席扱いとなる事例も多数報告されており、制度面から見ても安心して選べる教材といえます。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容・教材構成・評価方法のすべてが文部科学省の学習指導要領に準拠しており、そのため学校と同等レベルの学びが提供されていると判断されやすい設計になっています。
教材の内容が「教科書と一致している」だけでなく、子どもの進捗状況がシステム上で記録・確認できるため、保護者や学校が「どこまで学んでいるか」「どれくらい理解しているか」を把握しやすいのも特長です。
こうした構造が、家庭学習を学校の授業の代替として認めてもらいやすくしている理由の一つです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、小中高すべての学年で、学習指導要領に完全準拠して作られています。
これにより、学校の授業と同じ単元を同じ順番で学べるだけでなく、定期テストや学年末試験にも直結した内容になっています。
教科書に対応した内容だからこそ、学校の学習とすららの家庭学習が矛盾なくリンクしやすく、先生や教育委員会にも「学校の代わりとして活用できる教材」として受け入れられやすいのです。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
単なる動画視聴型の教材とは違い、すららは「問題演習→診断→フィードバック→再学習」というサイクルがシステム化されているため、継続的な評価が可能です。
学習ごとに点数が記録されたり、コーチからのコメントが届いたりすることで、子ども自身も「自分がどう成長しているか」を可視化できます。
この評価機能は、保護者や学校側が「この子はしっかり学んでいる」と判断する根拠にもなるため、出席扱いの申請や進級認定の支援材料としても非常に有効です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは文部科学省が定める「ICT教材を活用した自宅学習」に対応しており、学校側の承認を得ることで不登校児の「出席扱い」が認められる可能性があります。
これは、自宅での学習を通じて学校教育に準じた学びが継続されていると判断された場合に適用される制度です。
ただし、これは自動的に適用されるものではなく、保護者が学校としっかり連携し、所定の手続きを行う必要があります。
ここでは、すららを使って出席扱いを受けるための申請手順を4つのステップに分けてご紹介します。
実際の運用や条件は自治体や学校によって異なる場合があるため、柔軟に対応できるよう心構えしておくと安心です。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に行うべきは、現在通っている学校の担任や校長先生との相談です。
いきなり「出席扱いにしてください」と申し出るのではなく、「自宅でICT教材を使った学習を継続している」「すららという教材を使っている」など、今の学習状況を丁寧に説明することが大切です。
文部科学省のガイドラインでは、「学習の実態があること」「学習成果の確認ができること」が出席扱いの要件とされているため、それを満たすことを前提に話を進めていく必要があります。
また、学校ごとに必要な書類や条件が異なるため、担任の先生や学年主任を通じて、まずは学校内での対応方針を確認しておくとスムーズです。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、学習の実態を証明する書類や、医師の意見書が必要になるケースもあります。
すららの場合、学習記録や進捗レポートを活用することで、家庭学習の様子を客観的に提出することができますが、それだけで十分かどうかは学校の判断に委ねられます。
担任や校長先生と相談しながら、学校で用意する申請書類や保護者が記載する同意書など、具体的に何が求められるのかを確認しておくことが大切です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の原因によっては、医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。
とくに、精神的な不安や適応障害など、医療的なサポートが関係する不登校では、学習活動を続けることが望ましいといった内容を、医師から文書で示してもらうことが求められるケースがあります。
これは学校が「なぜ通学できないのか」「学習継続が本当に可能なのか」を判断するための材料となるため、必要に応じて診察を受け、医師と相談しながら意見書を準備するとよいでしょう。
学校側が診断書を強く求めている場合には、協力的な医師に相談することが安心につながります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
すべての不登校に診断書が必要というわけではありませんが、精神的な不安や発達特性による不登校など、学校が「医学的根拠のある不登校」として判断するためには、診断書が役立ちます。
提出を求められた場合は、診断書が準備できないことが理由で出席扱いの申請が進まないケースもあるため、可能であれば早めに医療機関に相談しておくと安心です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書や意見書を作成してもらう際は、「現在の不登校の状態」と、「在宅での学習継続が望ましい」という2点を必ず記載してもらいましょう。
これは出席扱いを受けるうえで非常に重要な内容であり、医師にそのまま伝えることでスムーズに進められます。
精神科や心療内科、小児科など、不登校を理解してくれる医師のもとで相談するとより安心です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでは、日々の学習進捗やログイン記録を自動で保存しており、それを保護者の管理画面から「学習記録レポート」として出力できます。
このレポートを担任または校長先生に提出することで、家庭での学習の実態を示す証拠となります。
レポートには、教科ごとの学習時間、進捗状況、理解度の推移などが記録されているため、「どれだけ学んでいるか」「継続して学んでいるか」が一目でわかります。
申請にはこのようなデータが非常に役立つため、出席扱いの申請時には必ず活用したい資料です。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
学習レポートは、すららの保護者ページからPDFでダウンロードできます。
どの単元を学習したか、学習時間、理解度などが一覧で表示されているため、学校側に提出する資料として非常に信頼性があります。
提出時は、事前にどのフォーマットが望ましいかを学校に確認しておくと安心です。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを申請する際には、学校で所定の申請書類を作成することになりますが、その記入に保護者が協力する場面もあります。
とくに、在宅学習の状況や教材の詳細については、保護者が一番よく把握しているため、学校と連携しながら申請書を整えていくのが理想です。
記載内容について不明な点があれば、学校に相談しながら進めましょう。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
すべての資料や申請書がそろったら、最終的に「学校長の承認」が必要になります。
ここで承認されることで、すららを使った在宅学習が正式に「出席扱い」として認められることになります。
自治体によっては、さらに教育委員会に申請が必要な場合もあるため、その際には学校側が窓口となってサポートしてくれることがほとんどです。
提出から承認までは多少の時間がかかることもありますので、余裕を持って進めていくことが大切です。
焦らず、学校との連携を大事にしながら、一歩ずつ進めていきましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的に「出席扱い」となるかどうかは、校長先生の判断に委ねられます。
教材の学習実績や学びの継続性が認められれば、すららを使った在宅学習が出席としてカウントされる可能性が十分にあります。
そのためにも、事前の記録提出や丁寧な説明がとても重要です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、出席扱いの承認に教育委員会の判断が必要な場合もあります。
このときは、学校が窓口となって申請してくれることが多いため、保護者は必要な情報や書類を整える形で支援しましょう。
学校との良好な関係が、手続きのスムーズさに直結します。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
「学校に通えていない=すべてが止まってしまう」と思いがちな不登校の悩みですが、実は文部科学省のガイドラインにより、一定の条件を満たすと自宅学習も「出席扱い」として認められるケースがあります。
そして、この制度の対象となる代表的な教材のひとつが「すらら」です。
すららは、文部科学省が推奨するICT教材として多くの自治体や学校でも活用されており、不登校でも学びを継続していることを証明しやすい環境が整っています。
出席扱いが認められることで、学校に通えない期間が評価上のマイナスとならず、進学時の内申や学習の遅れに対する不安を大幅に軽減できます。
ここでは、すららを活用することで得られる出席扱いの具体的なメリットについて、3つの観点から紹介していきます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校になると最も気になるのが「内申点」への影響ですが、すららのようなオンライン教材を使って継続的に学習している場合、学校との連携次第で出席扱いとして認められることがあります。
これは文部科学省が示す「ICT等を活用した自宅学習による出席扱い制度」に基づいた取り組みで、学校長の判断のもとで実施されます。
出席日数が一定水準を保てると、授業態度や学習意欲の評価においても不利になりにくく、結果として内申点の低下を防げるのです。
特に中学3年生では、高校入試において内申点が合否に直結するため、これは大きな安心材料になります。
通学できない期間があっても、学びを止めないという姿勢が評価され、進学の選択肢も広がっていきます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は、出席日数・提出物・授業態度などの積み重ねで評価されます。
不登校の場合は出席日数が足りなくなりがちですが、すららでの学習を「出席扱い」として認めてもらえれば、欠席としてカウントされずに済みます。
その結果、内申点に悪影響を与えるリスクが大きく減ります。
学校と連携を取りながら記録を残していくことで、学習の継続性も証明しやすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いが認められることで、「出席日数が少ないから推薦は難しいかも」といった不安も軽減されます。
内申点がしっかり確保できれば、公立高校や私立の推薦枠など、さまざまな選択肢にチャレンジできるようになります。
不登校経験があっても、学習が継続していた実績があることは、進学先にとってもプラスの要素として捉えられることが多いです。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
学校に行けていない状態が長引くと、子ども自身が「もうついていけないかも」「授業に戻れない」と不安を感じやすくなります。
しかし、すららを利用して日々の学習を積み重ねていけば、学校のカリキュラムに沿って知識を補えるため、大きく遅れることはありません。
すららは無学年式なので、苦手な単元は何度でも戻って学び直すことができ、理解が進めば学年を超えて先取りも可能です。
「今できることをやっている」という実感が持てることで、不登校による焦りや劣等感が薄れ、心に余裕が生まれます。
保護者から見ても、家庭での学習環境が整っていることは安心材料となり、学校との再接続への準備にもなります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
不登校の期間が長引くほど、授業の内容が進んでしまい「自分だけ遅れている」というプレッシャーを感じる子が多くなります。
しかし、すららなら自分のペースで何度でも見直しができるので、「ついていけない」という不安を解消できます。
授業の予習・復習も可能なので、登校再開時にもスムーズに授業に戻ることができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
すららを活用して毎日コツコツ学習できるようになると、「自分は何もしていない」という無力感から抜け出すことができます。
これが自己肯定感の回復につながり、不登校の改善にも良い影響を与えることがあります。
「できることをやっている」という手応えは、子どもにとって心の支えになるのです。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが不登校になると、親として「このままで大丈夫かな」「将来に悪影響はないだろうか」といった不安がつきまとうものです。
すららを導入することで、家庭に学習のペースが生まれ、日々の過ごし方にもリズムが出てきます。
また、すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習支援スタッフがついており、保護者に代わって学習計画を立てたり、進捗のフォローをしてくれるため、親が一人で抱え込む必要がなくなります。
学校とも連携しながら、家庭・学校・コーチの三者で協力体制を築くことができるため、「自分たちだけで何とかしなければ」というプレッシャーから解放されます。
子どもの不登校に悩むご家庭にとって、心の支えになる存在です。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、学習の進捗状況をすららコーチが共有・把握しているため、学校側とも協力しやすい環境が整っています。
保護者がすべてを背負う必要がなく、第三者が入ることで、冷静に対応ができるようになります。
「誰にも相談できない」と感じていた保護者にとって、大きな心の支えになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校のお子さんにとって、家庭での学習が「出席扱い」として認められるかどうかは、大きな意味を持ちます。
中でもすららは、文部科学省のガイドラインにも沿った学習支援ツールとして、全国の学校や自治体で評価されており、実際に出席扱いとして認められた事例も数多くあります。
しかし、すららを活用した学習が必ずしも自動的に「出席」としてカウントされるわけではなく、学校側や医療機関との連携、必要な手続きや配慮が不可欠です。
ここでは、すららを使って出席扱いを目指す際に気をつけたいポイントについて、事前に確認しておくべきことを詳しくご紹介します。
安心して手続きを進められるよう、保護者として知っておきたい大切な注意点をまとめました。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを使った家庭学習を「出席扱い」にしてもらうには、まず学校側の理解を得ることが欠かせません。
これはすららに限らず、すべてのICT教材に共通して言えることですが、学校がその教材の内容や信頼性を理解していないと、出席扱いの判断が難しくなるからです。
すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材であり、正式な教育支援ツールとして多数の実績があります。
そのため、学校側に対しては「文科省の方針に基づいた学習であること」や「学習記録が客観的に提出できること」など、丁寧に説明することが大切です。
担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生にも早めに相談しておくことで、スムーズに理解と協力が得られるケースが多くなります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
学校側は、教材が「正式な教育支援の手段」として認められるものかどうかを非常に重視します。
すららは、文部科学省が定めた「出席扱いに関するガイドライン」の基準を満たしている教材であり、その点をきちんと伝えることで、学校側の理解を得やすくなります。
「文科省が推奨している形式の教材を使用している」という事実は、保護者にとっても強力な後ろ盾となりますので、説明の際にはこの点を忘れずに伝えることが重要です。
パンフレットや公式サイトの説明資料なども併せて活用すると、より説得力のある説明ができます。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校への相談は、担任の先生だけで完結するとは限りません。
出席扱いの最終判断をするのは、校長先生であることが多いため、教頭先生や学年主任、特別支援教育コーディネーターなど、関係する先生方にも早めに情報共有しておくことが大切です。
その際、すららの公式資料や学習記録サンプルなどを印刷して持参すると、具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。
学校側の協力を得るには、こちらからの丁寧な情報提供と、早めの相談・調整が鍵を握ります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いが認められるには、家庭学習の実施状況だけでなく、「なぜ登校が困難なのか」という医学的な根拠が必要とされるケースがあります。
特に、不登校の理由が体調不良や精神的な要因(たとえば発達障害、適応障害、起立性調節障害など)である場合、医師による診断書や意見書の提出が求められることがあります。
すららのように優れた教材であっても、「なぜ通学できないのか」「家庭学習が適している理由」が説明できなければ、出席扱いが認められにくくなるため、早めに医療機関と連携して準備をしておくのが安心です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側が出席扱いを判断する際、「本人の状態が学校環境に適応できない医学的根拠があるか」は非常に重要なポイントになります。
体調不良、発達障害、精神的ストレス、起立性調節障害などが理由で登校できない場合、それを第三者である医師が診断書や意見書という形で証明することが求められます。
特に公立校では、医師の意見書がないと手続きに進めないことも多いため、家庭での話し合いと並行して、通院先の医師への相談を早めに始めるのがおすすめです。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師に診断書を依頼する際は、ただ「書いてほしい」とお願いするのではなく、出席扱いを希望していること、そのために医師の意見書が必要であることを丁寧に伝えることが大切です。
普段の通院先であれば、子どもの様子を把握してくれているため、スムーズに対応してもらえるケースも多く見られます。
あらかじめ学校側が求めている内容を整理しておくと、医師もより適切な内容で記載しやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師が診断書を作成する際、単に病名を書くのではなく、子どもが家庭学習に意欲的に取り組んでいること、すららのような教材を活用して学習が継続できていることなどを、保護者から具体的に説明しておくと、内容に深みが出て説得力が増します。
医師の視点から「この子には今は家庭学習が最も適している」と記載してもらえると、学校側も前向きに出席扱いの検討がしやすくなります。
信頼できる医師と連携しながら、前向きな形で診断書を作成してもらうことが大切です。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを活用して出席扱いを申請する際に、最も重要なポイントのひとつが「学習内容と時間が学校の水準に近いかどうか」です。
家庭学習だからといって、自由に勉強するだけでは出席認定は難しいことがあります。
文部科学省のガイドラインでも、「自宅で行う学習が、学校での授業と同等であること」が条件とされており、単なる読書やワークブックだけの学習では不十分です。
すららは、学習指導要領に沿った全教科対応のオンライン教材であり、日々の学習記録や単元ごとの達成状況がしっかりと記録される仕組みになっているため、出席扱いの要件をクリアしやすい設計です。
ただし、実際の学習の取り組み方にも注意が必要です。
「どれだけの時間を学んでいるか」「内容に偏りはないか」など、家庭での取り組み方次第で学校側の判断が変わる可能性があるため、以下の点にも気をつけて活用していくことが大切です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校の出席扱い制度では、子どもが家庭で取り組む学習が「授業と同じような内容・レベル」であることが求められます。
たとえば、ただのプリント学習や市販のワークブックだけでは、「授業に準じた」とみなされず、出席扱いが認められないケースもあります。
その点、すららは文科省の学習指導要領に準拠しており、教科書対応の内容を自分のレベルに合わせて学習できるので、制度要件に適した教材とされています。
さらに、動画授業・ドリル・評価の3ステップで構成されているため、単なる自習とは異なり、「体系だった授業」として評価されやすいのがポイントです。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いを申請する際、学習時間も大きな判断材料のひとつとなります。
すららは短時間でも取り組める設計になっていますが、出席扱いを視野に入れるなら、学校の授業に近い1日2〜3時間程度の学習時間を確保するのが理想です。
もちろん体調や集中力とのバランスもあるため、無理に詰め込む必要はありませんが、「定期的に学んでいる」「一定の学習リズムがある」ことを示すことが大切です。
すららの学習記録は自動保存され、学習時間もレポートに反映されるため、学校への説明資料としても有効活用できます。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
学校の授業では、国語や算数・数学だけでなく、理科・社会・英語などもバランスよく学ぶことが前提となっています。
そのため、家庭学習でも「特定の教科だけ」進めている場合、学校側から「学習の偏りがある」と判断され、出席扱いが認められにくくなることがあります。
すららのように、主要5教科すべてに対応している教材であれば、バランスの良い学習を無理なく実践できるのがメリットです。
コーチと相談しながらスケジュールを組むことで、苦手な教科にも自然に取り組めるように設計されているので、教科間の偏りを防ぎやすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
すららを活用して出席扱いを目指す場合、学校との定期的な連携がとても重要です。
どれだけ学習していても、学校側がその実態を把握できなければ、出席として認定することは難しくなります。
そのため、すららでの学習状況を定期的に共有し、学校が「学習が継続されている」と判断できる状態を保つことが大切です。
保護者が定期的に担任の先生と連絡を取り合い、進捗報告や今後の予定についてすり合わせを行うことで、学校側の安心感にもつながります。
とくに、不登校の期間が長くなっている場合は、学習以外の状況についても簡単に近況報告をしておくと、関係性が円滑に保たれます。
出席扱いを実現するためには、家庭と学校がチームのように協力し合う姿勢が大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
出席扱いが認められるには、単に「学習している」だけでなく、その内容が学校側と共有され、教育活動として認められる必要があります。
すららのようなICT教材を利用していても、その学習が誰にも確認されていない状態では、出席と見なされにくい傾向があります。
そのため、定期的な記録提出や、担任とのやり取りが制度活用のカギとなるのです。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには「学習レポート出力機能」があり、どの教科をどれだけ学習したか、理解度や学習時間を含めてひと目でわかる資料をPDFでダウンロードすることができます。
このレポートを月に1回、担任や学年主任に提出することで、継続的に学んでいることを証明できます。
報告の習慣をつけることで、学校との信頼関係も自然と築かれていきます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、保護者やお子さんと直接会って話すことで、学習状況をさらに具体的に把握したいと考える場合もあります。
そのような場合には、柔軟に家庭訪問や面談に応じることが大切です。
無理に構えなくても大丈夫ですが、丁寧な受け答えや、実際の学習画面を見せるだけでも安心材料になります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生と定期的に連絡をとることは、出席扱いの承認を得るうえで非常に有効です。
すららの学習状況をメールで報告したり、「今週はこの単元を進めました」といった短い報告だけでも、学校側に安心感を与えることができます。
先生の負担にならない範囲で、無理のない頻度でやり取りを続けていくことが理想です。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
学校によっては、校長先生の判断だけで出席扱いが認められる場合もありますが、一部の自治体では教育委員会への申請が必須となっているケースもあります。
その場合は、学校が教育委員会への申請を代行する形で進められますが、資料や経緯の整理などで保護者の協力が必要になることもあります。
すららの学習レポートや、医師の意見書など、提出すべき資料をまとめる作業は少し手間がかかりますが、出席扱いの制度を活用するためには欠かせないステップです。
学校と二人三脚で、丁寧に準備を進めていきましょう。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合は、必要となる書類や記載内容について、学校としっかり打ち合わせしながら進めていくことが大切です。
どのような形式での提出が求められているか、どこまで詳細を記入するかなど、学校が知っているノウハウを活かすことでスムーズな準備が可能になります。
保護者がひとりで抱え込まず、学校に相談しながら進めることが成功への近道です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららは、文部科学省が示すガイドラインに基づき、自宅学習でも「出席扱い」にできるICT教材として多くの学校に導入されています。
ただし、すららを使っているからといって、自動的に出席扱いになるわけではなく、学校側の理解と判断が必要になります。
そこで重要なのが、保護者や本人が積極的に「出席扱いを申請するための準備」をすることです。
申請の成功率を高めるには、すららの特長や過去の事例をうまく活かすことがカギとなります。
ここでは、実際にすららを使って出席扱いを認めてもらった家庭が行っていた「成功のポイント」を4つご紹介します。
準備や対応をひとつずつ丁寧に行うことで、学校側の理解も得やすくなり、出席日数の確保につながっていきます。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いを承認するうえで最も気になるのが「前例の有無」です。
教育現場では、他の自治体や学校で実際に導入されている例があるかどうかが判断材料になることが多いため、「すららで出席扱いになった事例」をこちらから示してあげると話が通りやすくなります。
実際に、すららの公式サイトには、過去にすららを活用して出席扱いが認められたケースが具体的に掲載されています。
これを印刷して学校に持参することで、学校側も「すでに実績のある教材なのだ」と納得しやすくなります。
また、文部科学省のガイドラインと照らし合わせた説明ができると、さらに説得力が増します。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
「うちの学校では前例がないから難しいかもしれない」と学校側が不安を示すことは少なくありません。
その際には、すららを使って出席扱いになった他校の事例を紹介することが非常に効果的です。
公式サイトや導入事例ページから具体的な学校名や実施方法が分かる資料を印刷し、担任や校長先生に見せることで、学校側の不安や疑問を取り除きやすくなります。
実績の提示は、学校の判断を後押しする大きな材料になります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式ページでは、過去に出席扱いとして認められた学校のインタビューや実践事例が掲載されています。
こういった客観的な情報を紙で印刷して持っていくと、口頭だけの説明よりも説得力があり、スムーズに話が進む可能性が高くなります。
面談や三者懇談の場で配布すれば、資料としても役立ちます。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの承認には、「本人が主体的に学習に取り組んでいるか」が重要な判断材料になります。
いくら教材の質が高くても、本人にやる気が感じられなければ、学校側も判断をためらってしまうことがあります。
そのため、保護者だけでなく、子ども自身が「自分で頑張っている」ことを伝える工夫が必要です。
すららでの学習後に書いた感想や、これからの目標などを簡単にまとめたものを提出することで、「この子は真剣に取り組んでいる」と学校にアピールできます。
また、面談の場に本人も参加し、自分の言葉で気持ちを話すことで、より強い印象を与えることができます。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学校に対して、本人が学習に前向きであることを伝えるには、「自分の言葉」が一番の説得材料です。
すららを使ってどのような勉強をしたか、どこが難しかったか、どんなことができるようになったかなどを子ども自身に書いてもらい、学校に提出すると良い印象を与えられます。
文字数や表現の上手さよりも、本人の気持ちが伝わることが大切です。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
三者面談や個別の保護者面談の機会があれば、できるだけ本人も同席させて、自分の声で思いを伝えることが重要です。
恥ずかしくても「頑張っています」「続けたいです」と一言でも言えると、学校側の印象がガラリと変わることがあります。
自発的な意志のある学習は、出席扱いの承認を後押しする要素になります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱い制度を申請する際、学校が最も重視するのが「学習の継続性」です。
「毎日5時間やります」といった無理な計画よりも、本人の体調や生活リズムに合わせて現実的に続けられるスケジュールのほうが信頼を得やすくなります。
すららでは、専属のすららコーチが在籍しており、学習スケジュールの作成を一緒に行ってくれます。
子どもの理解度や集中力に応じて、無理なく習慣化できるペースを提案してくれるため、その計画をベースに学校へ申請することで、説得力のある資料として提出できます。
大切なのは「続けられる計画を立てること」です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
「週に◯回、1日◯分」などの学習計画は、できるだけ本人の性格や集中力に合ったものにすることが大切です。
無理な目標ではすぐに続かなくなり、逆に「続けられていないから出席扱いは不可」と判断されてしまうリスクもあります。
短くても継続できる内容が一番です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららコーチは、子どもの特性や学習ペースを見ながら、最適な学習計画を一緒に考えてくれます。
経験豊富なスタッフが担当してくれるため、親だけでは気づかないポイントにも配慮してもらえるのがメリットです。
その計画を学校に提出すれば、より信頼性の高い提案として受け入れてもらいやすくなります。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
すららでは、学習支援を担当する「すららコーチ」が出席扱いの申請に必要なサポートもしてくれます。
たとえば、学校に提出する学習の実績レポートや、進捗を示す記録などを作成・提出する際には、コーチが適切な形でアドバイスをくれるため、不慣れな保護者でも安心して手続きを進めることができます。
また、学校とのやり取りにおいて疑問点があれば、どう説明すればよいか相談することも可能です。
一人で悩むのではなく、プロのサポートを受けながら申請に臨むことで、成功の確率もぐっと高まります。
すららを単なる教材としてではなく、「連携型の学習支援」として活用するのがポイントです。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学校に提出する「学習記録」「報告書」「週次レポート」などは、すららのコーチが必要に応じてアドバイスやテンプレート提供をしてくれます。
どのように記入すればいいか迷ったときも相談できるので、不安なく進められます。
保護者だけで申請するより、専門家の支援があることで説得力が増します。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららがうざいという口コミがある理由について、考えてみましょう。
このアプリに対する批判はさまざまですが、一般的な理由としては、ユーザーが実際に利用した際の課題や不満が挙げられます。
たとえば、広告が多いことや、使いにくい機能があること、またはサポートが十分でないと感じることなどが挙げられます。
いずれにせよ、ユーザーの声は重要であり、改善点を見つける上で貴重な手掛かりとなります。
それぞれの声に耳を傾け、より良いサービスを提供するために取り組んでいくことが大切です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
発達障害の方々がスキルを向上させ、自立した生活を送るためには、適切な支援が不可欠です。
そこで、すららの発達障害コースの料金プランについて詳しくお伝えいたします。
すららでは、発達障害を持つ方々が必要とするサポートを提供することを使命としています。
私たちは、個々のニーズに合わせたプランを提供し、専門的な指導やサービスを通じて、クライアントの成長と自己実現を支援しています。
料金プランに関して、すららでは一律の価格設定ではなく、個々のケースに合わせたカスタマイズが可能です。
そのため、まずはお問い合わせいただき、ご希望や必要な支援内容をお聞かせいただくことで、最適なプランと料金設定をご提案させていただきます。
お支払いに関しても、分割払いや医療保険の適用など、お客様のご要望に合わせた柔軟な対応が可能です。
費用についてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
すららの発達障害コースは、クライアントの成長と幸福を第一に考え、費用面での負担を最小限に抑えたサービスを提供しています。
ぜひ、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
不登校児童の保護者の皆様にお知らせします。
すららのタブレット学習がご自宅で不登校のお子様にも出席扱いとなるかどうかについて多くの疑問が寄せられております。
すららのタブレット学習は革新的な教育プラットフォームであり、学習内容が的確かつ効果的な方法で提供されます。
しかし、不登校の児童の出席扱いについては、教育機関や学校の方針に準じる必要があります。
不登校の児童がすららのタブレット学習を通じて出席扱いになるかどうかは、各学校や地域の教育委員会のガイドラインに基づいて決定されます。
例えば、一部の学校や教育機関は、オンライン学習を認めており、それによって出席率が算出される場合があります。
しかし、全ての学校や地域が同じ方針を持っているわけではないため、具体的なガイドラインは各教育機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
また、すららのタブレット学習は児童の学習支援や居場所への配慮を行っており、不登校の児童にも適した環境を提供しております。
保護者の皆様もお子様の学習状況や不登校の理由について、教育機関との円滑なコミュニケーションを大切にすることが重要です。
不登校のお子様が適切な学習環境で成長できるようサポートいたします。
最終的な判断は、不登校の児童をサポートする教育機関や関係者が行うべきです。
すららのタブレット学習は有益な学習ツールであり、不登校のお子様にも教育の機会を提供する可能性があります。
しかし、その適用方法や出席扱いに関する具体的な規定については、関係機関との連携が不可欠です。
保護者、教育機関、関係者が連携し、お子様の教育に最適なサポートを提供できるよう努めて参ります。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日は、弊社のキャンペーンコードの使い方についてご案内させていただきます。
弊社のキャンペーンコードをご利用いただく際には、以下の手順に従っていただくことが必要です。
まず、お支払い手続き画面に進んでいただき、プロモーションコードを入力する欄がございます。
そちらに、お持ちのキャンペーンコードを正確に入力してください。
その後、適用ボタンをクリックすることで、割引や特典が適用されることでしょう。
注意していただきたいのは、キャンペーンコードは一度のご注文につき一度しかご利用いただけないことです。
ご了承ください。
弊社では、定期的に様々なキャンペーンを実施しており、お客様にさまざまな特典をご提供しています。
そうした機会を有効活用いただき、ますます便利で充実したサービスをご利用いただければ幸いです。
どうぞお客様のライフスタイルに合ったプランを見つけ、すららをご活用いただけますようお願い申し上げます。
引き続きのご愛顧を心よりお待ち申し上げております。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららをご利用いただき、ありがとうございます。
退会手続きが必要になった場合、お客様を支援するために、退会方法について詳細をご案内いたします。
退会手続きは、以下のステップに従って行うことができます。
まず、退会をご希望の場合は、すららの公式ウェブサイトにログインしてください。
ログイン後、画面右上にあるプロフィールアイコンをクリックし、表示されるメニューから「アカウント設定」を選択してください。
アカウント設定ページで、画面下部に「アカウントの削除」または同様の表記がある場合がありますので、それをクリックしてください。
次に、アカウントの削除手続きを進めるために、システムが要求する情報を入力してください。
会員登録時に使用したメールアドレスやパスワードを入力することが必要となります。
その後、退会理由やフィードバックを提供するかどうかを選択し、必要事項を記入してください。
最後に、入力した情報を確認し、退会手続きを完了してください。
システムによっては、退会手続きの最終確認のために再度パスワードの入力を求められることがありますので、ご注意ください。
手続きが完了すると、アカウントの削除は確定されます。
もしも退会手続きに関してご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にカスタマーサポートにお問い合わせください。
すららをご利用いただき、誠にありがとうございました。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの利用にあたっては、基本的に「入会金」と「月額の受講料」のみで利用を開始することができます。
その他に、教材の購入費や機材のレンタル料などが必須でかかることはありません。
学習はすべてオンライン上で完結できる仕様になっており、テキストの購入やプリントアウトも不要な設計になっています。
また、タブレットやパソコンなどの端末は各家庭で準備する必要がありますが、それもご家庭にある機器で対応可能です。
すららの学習システム自体は、WEBブラウザを通して使えるため、特別なアプリを購入する必要もありません。
サポート費やコーチ料なども月額料金に含まれているため、「シンプルな料金体系でわかりやすい」と保護者の方からも好評です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1人1契約を基本とするサービスですので、1人分の受講料で兄弟複数人が同時に使用することはできません。
学習の進捗や理解度、診断結果、すららコーチのサポートなどは、あくまで一人ひとりに最適化されて提供されるため、アカウントは個別に管理されます。
ただし、すららは「兄弟割引」や「2人目以降の割引」などのキャンペーンを行っている時期もありますので、兄弟での受講を検討している場合は、公式サイトで最新の情報を確認すると良いです。
学年や学力に応じて個別のカリキュラムが必要になることが多いため、学習の効果を最大限に引き出すためにも、各お子さまごとに専用のアカウントで学習するのが安心です。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには「英語」の教科が含まれています。
英語学習は、アルファベットの基礎から始まり、フォニックスや日常会話、簡単な英語の読み書きまで幅広く対応しており、初めて英語を学ぶ小学生にもわかりやすい内容になっています。
また、アニメーションを使った授業なので、音や視覚で覚える工夫がされており、発音やリスニングにも自然と親しむことができます。
英語に苦手意識を持っているお子さんでも、「話す・聞く・読む・書く」のバランスを大切にしたカリキュラムになっているため、無理なく力をつけていくことができます。
英語を学校の授業より早めに始めたい方にもぴったりの内容です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の特長の一つが、「すららコーチ」と呼ばれる専任の学習サポーターによる手厚いフォローです。
受講開始時には、お子さまの現在の学力や生活リズム、苦手科目などを細かくヒアリングし、その情報をもとに個別の学習スケジュールを作成してくれます。
学習開始後も、毎月の進捗状況を確認しながら必要に応じてアドバイスをくれるので、途中でつまずいても安心して続けられる体制が整っています。
保護者との連携も密にとってくれるため、「どこまで進んでいるのか」「苦手をどう克服するのか」といった点も分かりやすく、学習全体を家庭と一緒に見守るパートナーとしての役割を果たしてくれます。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回の記事では、すららが不登校でも出席扱いになるかについて、出席扱いの制度、申請手順、および注意点について詳しくまとめました。
不登校の生徒や保護者にとって重要な情報を提供できたことを嬉しく思います。
出席扱いの制度や申請手順を理解することで、不登校の生徒が適切に支援を受けることができるようになります。
また、注意点についても把握することで、問題を未然に防ぐことができるでしょう。
教育環境の改善や生徒一人ひとりのサポートにつながる情報提供ができたことを誇りに思います。
不登校は生徒や保護者にとって大きな悩みや負担となることが多いため、出席扱いの制度や申請手順を知ることで、その負担を軽減できるかもしれません。
教育機関との円滑なコミュニケーションや適切なサポートを受けることが、生徒の学び舎を守り成長に繋がる大切な要素となります。
今後も教育に関する情報を提供し、生徒や保護者の皆様の支援に役立てられるよう、さらなる情報発信に努めてまいります。
不登校の生徒が安心して学びを続けられるよう、私たちも全力でサポートしてまいります。