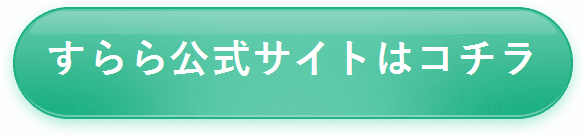すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
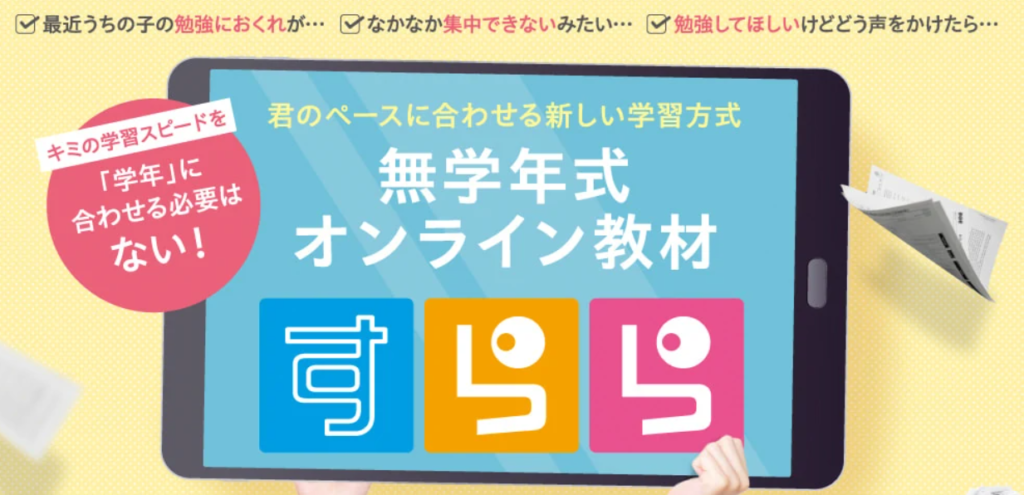
ネット上で「すらら うざい」といったキーワードを見かけることがありますが、実際に内容を調べてみると、特定の広告がしつこく表示されることや、子どもに勉強させたい親の期待と反発のギャップなど、周辺的な理由によるものであることがほとんどです。
実際にサービスとしての「すらら」は、学習に悩む子どもやその保護者から高い支持を得ており、発達障害や不登校などにも対応できる柔軟さや、保護者が学習を丸ごと任せられる「すららコーチ」の存在など、他のタブレット教材にはない強みがしっかりあります。
「うざい」と感じる人が一部いる一方で、継続的に成果を上げている家庭も多く存在しており、選ばれる理由には確かな理由があります。
ここでは、そんな「すらら」が人気を集めているおすすめのポイントについて、具体例とともに紹介します。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららは、一般的な学年制の教材とは異なり、無学年式で子どもの学力や理解度に合わせて自由に進められる点が最大の魅力です。
さらに、アニメーションキャラとの対話型授業によって、子どもが飽きずに学び続けられる仕組みになっています。
勉強が苦手な子や、不登校で学習が止まってしまった子にも対応しやすい教材として注目されています。
また、専属の「すららコーチ」が、個別に学習計画を立てて進捗を管理してくれるため、親が無理にスケジュールを管理する必要もなく、忙しいご家庭でも無理なく導入できます。
英語では3技能(聞く・読む・話す)に対応しており、レベルや興味に合わせた学習が可能です。
さらに、1契約で兄弟姉妹も一緒に使える仕組みになっており、家族単位での導入にも向いている教材です。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すらら最大の魅力のひとつが「無学年式」で学べるという点です。
これは、学校の学年にとらわれず、自分の理解度や得意・不得意に合わせて自由に進められる学習スタイルのことです。
たとえば、小学3年生でも中学1年の内容にチャレンジできたり、逆に苦手な算数の単元は小学1年の復習に戻ることもできたりします。
「学年の壁」がなくなることで、無理なく、でも確実に学力を積み上げていくことができるのが特徴です。
周りと比べて焦ったり、遅れを気にしたりする必要がなく、自分のペースを大事にしながら前向きに学習に取り組める環境が整っているのは、学びに悩むお子さんや不登校のお子さんにとっても大きな安心材料になります。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
すららは、学年という枠組みではなく「その子に合ったレベル」を大切にしています。
たとえば、「小4だけど算数は小2の内容でつまずいている」「英語は得意だから中学生レベルもやってみたい」といった個別の状況にも柔軟に対応できます。
学年で一律に進んでいく学校とは違い、すららは「自分にとってのベストなタイミング」で進められるため、ストレスやプレッシャーがぐっと減ります。
自分のペースを大事にできるからこそ、勉強が苦手な子でも「ちょっとやってみようかな」という気持ちを持ちやすく、継続しやすい仕組みになっています。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
すららの無学年式は、「戻る」も「進む」も自由自在です。
得意な教科や単元はどんどん先取りして進められるので、飽きずに学び続けることができますし、逆に苦手なところは時間をかけてじっくり復習できます。
「わからないところを何度でも繰り返せる」「理解したところはテンポよく進められる」という仕組みがあることで、子ども自身が学習をコントロールできる感覚を持ちやすくなります。
これは、学ぶことそのものへの自信にもつながり、「自分はやればできる」という成功体験を積み重ねやすくなるのです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの授業は、他のオンライン教材と大きく違って「対話型」のアニメーション授業です。
つまり、キャラクターの先生たちが、子どもに話しかけるような形で授業を進めてくれるので、受け身ではなく自然と「会話の中で理解していく」ような感覚で学べます。
この双方向性のあるスタイルが、飽きっぽいお子さんや集中力が続きにくいお子さんにもぴったりなんです。
しかもキャラがリアクションを取ってくれたり、褒めてくれたりするので、「もっとやってみようかな」と気持ちが前向きになりやすく、ゲーム感覚で楽しく勉強が続けられます。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
子どもにとって、「誰に教わるか」は意外と大事なポイントです。
すららでは、アニメーションで登場するキャラクターが「先生役」をつとめ、まるで一緒に勉強しているような感覚で進めてくれます。
「これはどう思う?」「ちょっと復習してみようか」といった問いかけが入りながら授業が進むため、子どもが自分で考える時間が生まれ、ただ動画を眺めているだけではない「参加型の学習」が実現します。
一人で黙々とやるよりも、キャラと一緒に学ぶスタイルの方が楽しいという子も多く、特に低学年や勉強が苦手な子にはとても相性の良い形式です。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
すららの授業は、文章だけでなく「図」「イラスト」「動き」を多用しているのが特徴です。
たとえば、算数の文章題であれば登場人物が動いたり、図形が回転したりして、目で見て理解できる工夫が施されています。
視覚的な情報があることで、「あ、なるほど」と感覚的に理解できる瞬間が増えるので、苦手意識のある子でも自然と内容が頭に入っていきます。
黒板に文字だけ書かれるような授業とは違い、視覚・聴覚の両方を使って学ぶことで、記憶にも残りやすくなっているのです。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
すららのキャラクターは、ただ説明するだけではなく、子どもが正解した時にはしっかりと褒めてくれます。
「よくできたね!」「すごいじゃん!」といったポジティブな声かけがあると、子どもは「もっと頑張りたい」と感じやすくなります。
特に、飽きやすい・集中力が続かないお子さんにとっては、この“褒め”のタイミングが大きなモチベーションになります。
楽しさの中にしっかりと学びがあるスタイルなので、「遊びの延長」として自然と続けられるのが、他の教材にはないすららの大きな魅力です。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
タブレット学習を導入するときに、多くの保護者が感じるのが「結局、親が全部見てあげないといけないのでは?」という不安です。
でもすららは、「すららコーチ」という学習サポートの専門スタッフがつくので、親の負担はほぼゼロに近づきます。
このすららコーチが、子どもの特性・学力・目標に合わせた学習計画を作成してくれるだけでなく、毎月の学習状況をチェックしてアドバイスをくれます。
保護者は「見守るだけ」でOKなので、忙しい家庭や教育に自信がないという方でも安心して利用できる仕組みです。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららに登録すると、すぐに専属の「すららコーチ」が付きます。
このコーチは、教育の知識と経験を持った専門家で、子どもの性格や学習傾向を見ながら最適なスケジュールを提案してくれます。
たとえば、「1日20分だけ」「月水金だけ」など、家庭の生活スタイルに合わせて計画してくれるので、無理なく続けられるようになります。
そして、計画を立てて終わりではなく、毎月の進捗を見ながら必要に応じて調整してくれる点も心強いです。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、テンプレート的なスケジュールではなく、その子の発達段階や個性をしっかり見たうえで、完全に個別化された学習プランを作ってくれます。
たとえば「集中力が15分しか持たない」「得意な教科は自分で進めたい」など、細かな要望にも応えてくれるので、子ども自身が無理なく、そして納得感を持って学習を進められるようになります。
「自分だけの先生がいる」安心感もあり、信頼関係が築かれることで学習意欲が高まる子も多いです。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
子どもが勉強中につまずいたとき、「これは親が答えていいのかな?」と悩んでしまうことってありますよね。
でもすららなら、そうした質問や相談はコーチに直接できます。
すららコーチとのやりとりは専用フォームで行われ、子ども自身が質問することもできますし、保護者が代わりに相談することも可能です。
疑問がすぐに解消される環境があることで、子どもも不安を感じずに学習を続けられますし、親としても「全部自分が答えなきゃいけない」というプレッシャーから解放されるのがとてもありがたいポイントです。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、学力に不安のある子どもや、発達障害・不登校といった課題を抱える子どもたちにも配慮された教材として、多くの保護者から支持されています。
授業形式は単なる動画視聴ではなく、対話型で双方向に進んでいくため、集中力が持続しづらい子どもでも飽きずに学習を継続しやすくなっています。
さらに、AIがリアルタイムでつまづきを解析してくれることで、「どこでつまずいたのか」「理解が浅いのはどの単元か」を自動で判断し、その子に合った問題を提示してくれるのが大きな魅力です。
学校のペースに合わなくても、すららなら自分のペースで戻り学習ができるため、無理なく取り組むことができます。
発達障害や不登校の支援実績も豊富で、実際に文部科学大臣賞を受賞していることからも、その信頼性の高さが伺えます。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、文部科学大臣賞を受賞した実績を持つ、信頼性の高い学習支援ツールです。
単に成績アップを目指す教材ではなく、学びづらさを抱える子どもたちの「わからない」に寄り添い、学び直しをサポートする設計が高く評価された結果です。
特に、不登校や発達障害といった個別の学習ニーズに対応できる仕組みを持っている点が、他の学習サービスにはないすらら独自の強みとなっています。
このような表彰歴があることで、「すららって本当に効果あるの?」と不安を抱える保護者にも安心して使ってもらえる材料になります。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
すららは、ADHD(注意欠如・多動症)や学習障害(LD)など、発達障害のある子どもにも配慮された設計となっています。
たとえば、短時間で区切られた単元、視覚と音声を活用したわかりやすい解説、そして繰り返し学習がしやすい機能などが充実しています。
こうした工夫により、集中力が続きにくい、忘れやすい、板書を写すのが苦手、といった特性を持つ子どもでも、自分のペースで安心して学習できる環境が整っています。
また、すららのAIは理解状況に応じて内容を調整してくれるため、子どもが一人で学んでいても「置いてけぼり」になりにくい点が大きなメリットです。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
すららは、不登校の子どもにも非常に親和性の高い教材です。
学校に行けない期間が長引くと、授業の進度から大きく遅れてしまい、「今さら勉強を始めても追いつけないのでは」と不安になる子どもも多いですが、すららは学年に縛られない無学年式のため、どこからでもスタートできます。
「小5だけど、小3の内容に不安がある」といった場合でも、自分の理解度に合わせて戻ってやり直すことができるので、精神的なハードルが非常に低くなります。
また、先生やクラスメイトとの比較がない自宅学習という環境も、不登校の子どもにとっては安心できるポイントのひとつです。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららの最大の特長のひとつが、「AIがつまづきを解析し、理解が浅い箇所を自動で出題してくれる」機能です。
通常の教材では、子どもが間違えた問題に対して親や先生が原因を探り、対策を立てる必要がありますが、すららではAIが瞬時に「この単元が弱い」と判断し、それに関連する基礎問題を出してくれる仕組みになっています。
これにより、子どもは自分が気づかない苦手を自然と克服していくことができ、保護者も過度に介入する必要がなくなります。
学習の流れが自動で組み立てられるため、迷わず続けやすいのも魅力です。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
すららでは、オンライン上で定期的に小テストや理解度チェックが行える仕組みが整っており、その結果はリアルタイムでAIが分析してくれます。
この分析により、「今、どの単元を理解していて、どこに苦手が残っているか」が可視化されるため、子ども自身も成長を実感しやすくなります。
保護者としても、日々の学習の進み具合や定着度をレポートで確認できるため、家庭での声かけや見守りにも活かしやすくなります。
結果を基に次に学ぶ内容が自動で提案されるので、無理なく着実にステップアップしていくことが可能です。
「ただやらせて終わり」ではなく、「どう変化したか」を数字で確認できることで、子どもにも達成感が生まれやすく、学習意欲の維持にもつながります。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららの小テストは、単に「できた・できなかった」を確認するためのものではなく、間違えた問題に対してその場ですぐにフィードバックが返ってくる設計です。
「なぜ間違ったのか」「どの考え方が間違っていたのか」といった説明がリアルタイムで表示されるため、理解が浅いまま次に進んでしまうことがありません。
このように、問題を解く→間違える→解説を見る→再挑戦するというサイクルが自然に組み込まれているため、理解の定着に非常に効果的です。
子どもにとっても「なんとなく覚える」ではなく、「ちゃんとわかって進める」という実感が持てるのが嬉しいポイントです。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
すららでは、一定の学習が終わると「定着度診断」というテストが実施され、AIがその結果をもとに学習内容の定着度を分析してくれます。
単に点数を見るだけでなく、どの単元の理解が不十分だったかを判定し、そのまま「復習すべき問題」を自動で組み立てて提示してくれます。
これにより、子ども自身が「何を勉強したらいいのかわからない」と迷うことがなくなり、親もサポートの負担が減ります。
苦手をピンポイントで潰していける仕組みが整っているため、着実に学力を底上げできるのが大きな特長です。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
学習の成果が「見える化」されるのは、保護者にとっても大きな安心材料です。
すららでは、子どもの学習進捗やテスト結果などを、定期的に保護者にレポートで配信してくれます。
これにより、「今日は何をやったのか」「どの教科が得意なのか」「つまずいている単元はどこか」といった情報が一目でわかるようになっています。
成績や進度を親子で共有することで、学習のモチベーションを高めたり、適切な声かけがしやすくなるのもメリットです。
忙しくて毎日の学習を細かく見られない保護者でも、すららのレポートを活用することで、学習の状況をしっかり把握することができます。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語は、学校の授業や一般的なタブレット教材とは一線を画しており、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能をバランスよく学べる構成になっています。
通常の教材では「聞く」や「読む」までしか対応していないことが多い中、すららでは音読練習や音声判定の機能もあるため、「話す」力を養うトレーニングまで行えるのが特長です。
また、アニメーション付きの解説で単語や文法をわかりやすく学べるため、英語に苦手意識のある子どもでも、自然と文法の基礎が身につきやすくなっています。
英検の5級〜3級レベルを目指す子にとっても効果的で、特にリスニングパートは実用的な英語音声で構成されているため、耳から英語を覚える習慣が無理なく身につきます。
英語の総合力を育てたいと考えているご家庭にはぴったりの教材です。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
すららの英語では、ネイティブスピーカーによるクリアで聞き取りやすい英語音声が使用されており、小学生のうちから本物の英語の音に慣れることができます。
特に、英語が初めてという子どもでも安心して取り組めるよう、スピードや発音に配慮された音声になっており、段階的にリスニング力を伸ばせる工夫がなされています。
英語に対する抵抗感が少ないうちに、本物の英語のリズムやイントネーションを聞き取る力を養っておくことで、将来的に中学・高校での英語学習にも良い影響が出てきます。
音読チェックでスピーキング練習ができる
すららの英語には、音読チェックの機能も備わっており、ただ聞くだけでなく「話す」練習もできます。
これにより、英語をアウトプットする力も自然に育っていきます。
特に、小学生のうちは恥ずかしさや間違いを恐れる気持ちが少ないため、音読練習を繰り返すことで発音やリズムがどんどん身についていくのです。
タブレットに向かって声を出すだけなので、家の中でも気軽に練習でき、ネイティブの音に近づく発音指導も受けられます。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
単語や文法の解説は、アニメーションを用いた視覚的な説明が特徴で、子どもが自然とルールを理解できるような工夫がされています。
教科書のような堅苦しさがなく、「なるほど、そういうことか!」と納得できるような場面が多いため、英語が初めての子にもおすすめです。
英検のリスニングや文法問題に対応した内容も多く、試験対策としても十分活用できる教材です。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、他のタブレット学習とは一線を画しています。
最大の特徴は「1契約で複数人が使える」という点で、兄弟や姉妹が一緒に利用しても、追加料金がかからない仕組みになっています。
たとえば、小学生のお兄ちゃんと中学生の妹がそれぞれのレベルで同時に使っても、それぞれ別契約をしなくてよいのです。
さらに、教科ごとに自分たちに必要な内容だけを選んで追加できるため、無駄のない料金設定が可能です。
家庭に複数の子どもがいる場合、こうした柔軟でコスパの良い料金体系は大きな魅力になります。
「1人あたりいくら」ではなく、「1家庭でどう使うか」という考え方で利用できるのは、すららならではのメリットです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららでは、契約者が1人であっても、同じ家庭内であれば兄弟・姉妹が一緒に使うことが可能です。
これは非常に珍しいシステムで、一般的なタブレット教材では、1人分ごとに別契約が必要になることがほとんどです。
すららでは、学習者ごとにログインIDを発行できるため、それぞれの学習履歴や進捗も個別に管理でき、成績レポートも分けて確認できます。
これにより、親としても子どもたち一人ひとりの学習状況を把握しやすくなります。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
実際の利用例として、小学4年生のお兄ちゃんと中学1年生の妹が、同じすららの契約内でそれぞれのレベルに合った学習を行っている家庭も多いです。
無学年式の教材であることに加え、兄妹それぞれに個別のカリキュラムが組まれているため、学力差があっても同じサービス内で効率よく学べるという利点があります。
追加契約が不要なので、家計的にも非常に助かるという声が多く聞かれます。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららは国語・算数(数学)・英語の3教科から必要な科目だけを選んで契約できます。
たとえば、「算数だけ苦手なので算数だけ追加したい」という場合にも対応できるため、無駄な支払いが発生しません。
家庭の方針や子どもの学力状況に応じて、必要な科目を柔軟に組み合わせられることが、結果として継続しやすさや満足度にもつながっているのです。
初期費用や更新費用も明確で、安心して始められるのも大きなポイントです。
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
「すらら うざい」といった言葉を見かけることがありますが、その多くは広告の表示頻度や、親が子どもに勧めすぎてしまったときの反発などに関係するものです。
実際の教材としての「すらら」は、家庭用のタブレット教材の中でも非常に評価が高く、特に「学習に不安がある子」や「学校に通えていない子」にとって、強い味方になってくれるサービスです。
一般的な教材とは違い、学年を超えて学べる「無学年式」に加え、プロの学習コーチが伴走してくれる「すららコーチ」の存在が、親にも子どもにも大きな安心を与えてくれます。
ここでは、そんなすららならではの他教材にはない大きなメリットを、丁寧にご紹介していきます。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
家庭用のタブレット教材は数多くありますが、「自学自習」が基本で、子どもだけに任せる形が多く見られます。
しかし、すららはそこに一線を画しており、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門家がついてくれるのが大きな特徴です。
このすららコーチが、子どもの特性・学習状況・ペースに合わせてオーダーメイドの学習スケジュールを作成し、毎月の進捗管理まで行ってくれます。
親が毎日声をかけたり、細かく進度をチェックしたりしなくても、プロの目で状況を見守ってもらえる安心感はとても大きいです。
特に共働き世帯や、教育に不安があるご家庭にとって、「任せられる相手がいる」ことは心の支えになります。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららでは、登録するとすぐに担当のすららコーチがつきます。
このコーチは、単なる学習アドバイザーではなく、教育や発達支援に関する専門知識をもった人材が担当しており、子どもの特性や生活スタイルを踏まえて最適なサポートをしてくれます。
コーチは、毎月の学習状況をもとにレポートを作成してくれるだけでなく、「今月はちょっと進みが遅いですね」「来月は少し復習を多めにしましょう」といったきめ細やかなアドバイスも届けてくれます。
親が見落としがちな部分にも気づいてくれる存在がいることで、子どもも安心して勉強を続けられる環境が整います。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
すららコーチが行うサポートの中心は、完全個別の学習スケジュールの作成です。
たとえば、「夜しか集中できない」「毎日は難しいけど週3日ならできそう」「1回15分しか集中できない」など、それぞれの子どもの生活パターンや得意不得意に合わせて、無理のない計画を立ててくれます。
子どもが自分で「これならできそう」と思えるスケジュールだからこそ、継続しやすく、達成感も得やすいのがポイントです。
また、計画は定期的に見直してくれるので、習い事や学校生活の変化にも対応できます。
勉強を押しつけられている感覚ではなく、自分に合ったやり方で進められることが、子どもにとっての大きな安心材料になっています。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららが高く評価されているもうひとつの理由は、不登校や発達障害といった「学びに困難を抱える子ども」への対応力です。
実際にすららは、文部科学省の推奨教材としても複数の自治体や学校で導入されており、不登校の子どもの学習支援として「出席扱い」にされることもあります。
また、ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動性障害)・LD(学習障害)などの特性を持つ子にも対応した設計になっており、AIによるつまずき診断や、柔軟な学習プランの提供など、本人に合った学び方ができる工夫が満載です。
他の教材では見落とされがちな“学び直し”や“自信を取り戻すプロセス”を、すららは丁寧にサポートしてくれるのです。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省が推進するICT教育の中でも、特に「特別な支援を必要とする児童生徒」向けに強みを持つ教材として、各地の教育委員会や公立学校で採用された実績があります。
不登校の子どもが自宅で「学び」を継続できるだけでなく、その学習内容が学校での出席と同等に扱われることもあるため、安心して取り組むことができます。
これは、家庭学習を「学校と同じ価値のある学び」として認めてもらえる制度であり、保護者にとっても非常に心強い仕組みです。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを利用して学習を継続していると、その記録を学校に提出することで「出席扱い」として認定してくれる学校が全国に増えています。
これは、すららが文科省のガイドラインに沿った学習管理ができるシステムを導入しているためで、学習時間や内容、理解度までしっかりとレポートに残すことができるからです。
「学校に行けていない=勉強していない」と見なされることなく、安心して家庭での学習を続けられるのは、不登校のお子さん本人にも、保護者にも非常に大きな支えになります。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
すららでは、発達障害の子どもたちにとって負担が少なく、理解しやすいように設計されたコンテンツが使われています。
例えば、ADHD傾向の子どもには集中力が続くように短いセクションでの構成、ASD傾向の子どもには視覚的な説明を多用するなど、学びやすい仕組みがたくさん詰まっています。
また、わからなかった問題はAIが即座に分析し、「どこでつまずいたか」を特定してくれるため、ただやみくもに進むのではなく、確実に「理解」を積み重ねていけるのがポイントです。
こうした配慮があることで、特性のあるお子さんでも無理なく、自信をもって勉強を進めていくことができるのです。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの最大の特長のひとつが、この「無学年学習」です。
一般的な学習教材では、学年ごとのカリキュラムが決まっていて「学年=レベル」とされることが多いですが、すららではその常識を取り払い、子ども一人ひとりの理解度に合わせて「戻り学習」も「先取り学習」も自由にできる仕組みになっています。
たとえば、小学5年生の子が2年生の算数に戻って復習したり、中学1年生が高校数学の導入を先に学んだりすることも可能です。
この自由度があることで、苦手をそのまま放置せず、かつ得意な分野はどんどん伸ばすことができます。
学校のペースについていけないと感じている子にとって、自分のペースで学べるこのシステムはとても大きな安心材料になります。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
無学年式の強みは、「今の学年」に縛られず、その子の「今の理解度」に合わせて学習できることです。
教科書の順序に従う必要がないため、「わからないところからやり直す」「得意なところは先に進む」という柔軟な学び方ができ、理解の抜け漏れをなくすことにつながります。
たとえば、小3でつまずいた単元を小5になって復習しても、すららなら違和感なく自然に取り組めます。
学習が自分ごとになりやすく、「分かった!」という実感を得られるタイミングも増えます。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害の特性を持つ子どもにとって、「わからないまま進んでしまう」ことは大きなストレスになります。
すららの無学年学習は、そういった不安を取り除くための工夫が凝らされており、子ども自身が「自分のペース」で学習できるように設計されています。
視覚的に理解しやすい解説や、つまづいたときに自動で戻る機能などが備わっており、保護者がつきっきりで教えなくても、安心して子ども一人でも学習が進められるようになっています。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららでは、学習の進め方が「AIによる分析」と「人間によるサポート」の2軸で構成されているのが特長です。
多くのオンライン教材では、AIによる自動出題や分析までは対応しているものの、その情報をもとにして「どのように進めるか」までサポートしてくれる人がいるケースは少ないです。
すららでは、担当コーチが子ども一人ひとりの学習傾向・特性・進度を見ながら、個別の学習プランを提案してくれます。
このAIと人のハイブリッド型サポートが、他にはない安心感と効率の良い学習を可能にしています。
保護者がすべてを管理しなくても、プロの視点で進め方を調整してくれるため、学習が定着しやすくなります。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIの診断機能は、子どもの解答状況やつまづき傾向をリアルタイムで分析し、「どこが苦手か」「次に学ぶべき単元はどこか」を導き出してくれます。
そのうえで、人間のすららコーチがそのデータをもとに、より細かいアドバイスや進捗管理を行ってくれるため、学習の質が格段に上がります。
この「人×テクノロジー」の組み合わせが、学力に不安がある子や、家庭でのサポートが難しいご家庭にとっても非常に大きな助けになります。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIは便利な反面、どうしても機械的な判断しかできないという限界があります。
たとえば「問題は解けているけど、集中力が続いていない」「やる気が落ちている」といった状況は、数字だけでは把握しづらいものです。
すららのコーチは、学習ログだけでなく子どもの性格や目標に応じて、学習量や難易度の調整をしてくれるため、ムリなく続けられる学習環境をつくることができます。
こうした細やかな人の目によるサポートが、継続率の高さにもつながっています。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
「紙じゃないと記述力は育たない」と思われがちですが、すららはあえて“紙を使わない”デジタル完結型でも、しっかりと記述力を育てる工夫がされています。
単なる選択問題ではなく、「理由を説明する」「考えをまとめる」タイプの問題が豊富に用意されており、子どもが自分の言葉で答えを書く練習が自然とできるようになっています。
記述内容に対してフィードバックが返ってくる設計になっているため、「書きっぱなし」では終わらず、書く力そのものが着実に伸びていきます。
将来的な受験や社会で必要になる「論理的に説明する力」を、小学生のうちから無理なく養えるのが、すららの大きな魅力です。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららの記述トレーニングでは、ただ文章を書くだけではなく、「理由を明確にする」「要点を整理して伝える」といった論理的な構成力を意識したカリキュラムが組まれています。
特に国語や社会では、問いに対して自分の考えを筋道立てて答える形式の問題が多く、「どう答えるか」を考える力が自然と身についていきます。
こうした記述型学習を日常的に取り入れている教材は珍しく、表現力を伸ばしたいご家庭にとっては非常に心強いサポートとなります。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
タブレット学習の多くは、「選択式」「計算重視」など操作がシンプルな設計が主流ですが、すららでは「読解→要約→記述」という一連の思考の流れをデジタル上で完結できる教材となっています。
入力式の記述問題に対応しているだけでなく、書いた内容に対する自動フィードバックも備わっているため、実際に書く力が身につきやすい構成です。
特に、紙教材と違ってその場で答えを見直せるのも利点で、復習の効率も高くなります。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
すららは、学習を一時的に中断しても、後からスムーズに再開できる仕組みが整っているのが大きな特徴です。
特に、不登校や発達障害のあるお子さんなど、「一定のペースで学び続けることが難しい」というケースでは、こうした柔軟な対応が非常にありがたいものです。
例えば、体調やメンタルの調子が不安定な時期には一時的に休んで、落ち着いたタイミングでまた学習を再開するといった使い方ができ、途中で止まってしまっても「取り残される」感覚がないのはすららの強みです。
また、すららは無学年式なので「どこまでやったか」に縛られることもありません。
本人のペースで学習できるからこそ、「やりたくなったときに、いつでも戻ってこられる」安心感が生まれるのです。
これは他の教材にはなかなか見られない、すらら独自のメリットです。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
すららは、学習履歴や進度がクラウド上に保存されているため、一時的にやめたとしても、再開時にはすぐに前の続きからスタートできる設計になっています。
紙教材のように「どこまでやったか分からなくなる」こともなく、ログインするだけで、いつでも自分の進度に合わせて学び直すことができるのです。
再登録などの面倒な手続きも不要で、アカウントを維持したまま一時停止し、再開したい時にまた取り組めるという柔軟さがあります。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害を抱えるお子さんにとって、毎日決まった時間に学習を続けるのが難しいことは珍しくありません。
体調や気分、生活リズムによって大きく学習意欲が左右されるため、「やる気があるときにだけ取り組める」スタイルの教材が非常に重要になります。
すららは、そういった子どもの特性に合わせて、自由なスケジュールで学べる設計になっており、休んでも罪悪感を感じずに済むという安心感があります。
保護者としても、「今日はできなくても、また明日がある」と思える環境はとても心強いです。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、単なる自宅学習用の教材という枠を超えて、教育機関や行政との連携を積極的に行っている教材です。
中でも注目されているのが「出席扱い制度」に対応している点です。
すららを使って自宅で学習している内容が、学校の授業の一環として認定され、出席扱いになるというケースが全国的に広がっています。
これは、文部科学省のガイドラインに基づいており、実際にすららを活用することで出席認定された実績が多数あります。
不登校や長期欠席の子どもにとっては、学校復帰の第一歩として、非常に大きな意味を持つ制度です。
本人の学習モチベーションにもつながり、保護者にとっても安心材料になります。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららでの学習は、文部科学省が示す「ICTを活用した学習支援」として、学校側が出席として認めるケースが増えています。
実際、すららを使用することで、学校に出席していない日数の一部または全部が「出席扱い」になる事例が報告されており、教育現場でもその実用性が高く評価されているのです。
この制度を活用すれば、無理に登校せずとも学習を継続できることが記録に残るため、学年進級や高校入試においても有利に働くケースがあります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、不登校支援教材として教育委員会や学校、病院などと連携して使用されるケースも多く、医療機関との協働で「教育支援プログラム」に取り入れられることもあります。
特に、入院中や長期療養中の子どもに対して、病院から学習指導の一環としてすららが導入される例もあり、その実績は全国各地で広がっています。
単なる家庭用の教材ではなく、専門機関と連携した「教育支援ツール」として評価されているのは、すららならではの強みです。
【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは、発達障害や不登校の子どもにも対応できる柔軟な無学年式教材として、多くの保護者から高評価を受けている一方で、「うざい」と感じてしまう人も一定数います。
その理由は、教材そのものの内容に加え、サポートの頻度や学習スタイルの個人差による「合う・合わない」が背景にあるようです。
特に、子ども自身の学習スタイルが「干渉されるのが苦手」「自主性を重視したい」といった傾向にある場合、すららの仕組みが逆効果に感じてしまうこともあります。
また、広告や勧誘の印象が強く残ってしまったケースや、期待したほどの学習効果を感じられなかった場合にも、不満の声が出やすくなります。
ここでは、すららに対して「うざい」と言われてしまう具体的な原因と、それに伴うデメリットについて、実際の利用者の感想も参考にしながら紹介していきます。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららでは、学習の定着をサポートするために専属の「すららコーチ」がつき、子どもごとの進度や理解度に合わせた声かけや学習指導を行ってくれます。
この仕組みは「親が管理しなくていい」「プロが見てくれるから安心」と評価されている一方で、毎週のように届くLINEやメール、時には電話連絡を「頻繁すぎる」と感じるご家庭もあります。
特に、自分のペースで勉強を進めたい子どもや、干渉されることにストレスを感じるタイプの子にとっては、「放っておいてほしいのに、コーチが口を出してくる」と受け取られてしまうことがあるようです。
こういったコミュニケーションの頻度が合わないと、「うざい」「しつこい」といった印象につながってしまうのです。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららコーチのフォローは、基本的には前向きなサポートですが、すべての子どもにマッチするとは限りません。
もともと自主的に取り組むタイプの子にとっては、「今日は何ページまでやりましょう」「ここがまだ終わっていませんね」といった連絡が、逆にプレッシャーや干渉と感じてしまうことがあります。
放っておかれた方が頑張れる子や、自分で管理したい子には、「いちいち言われるのが嫌だ」となりやすく、コーチ制度が仇になってしまうこともあるようです。
子どもの性格に合うかどうかは、体験で見極めるのが安心です。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららは、学習計画の自動生成機能やAIによる進捗管理が非常に優れており、どこから何をどの順に進めるべきかが明確に提示されます。
この機能によって、「次にやるべきことがわかる」「迷わず進められる」というメリットがある反面、「決まった通りにやらなきゃ」というプレッシャーにもつながることがあります。
特に、完璧主義タイプや時間に追われがちな家庭では、学習の自由度が少なく感じられたり、「やらされている感」が強まってしまうことがあるようです。
こうした心理的な負担があると、続けること自体がしんどくなり、「なんか合わない」「うざい」と感じてしまう結果にもつながります。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
すららのAIはとても優秀で、過去の回答状況や理解度に応じて個別に学習計画を提案してくれます。
しかし、この「個別カリキュラム」に対して、「今日は気が乗らない」「もっと復習したい」「自分で決めたい」と感じる子にとっては、選択の自由が奪われたように思えてしまうこともあります。
やるべきことが決められていることがモチベーションになる子にはぴったりですが、自由に学習したい子には、かえって負担に感じられるケースもあるのです。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららの授業はアニメーションを使ったキャラクターとの対話形式で進行するため、小学生の低学年〜中学年くらいにはとても人気があります。
ですが、逆に高学年〜中学生や思春期の子にとっては、「キャラが子どもっぽい」「話し方がくどい」「うざく感じる」といった印象を持たれることもあるようです。
アニメの演出が楽しいと感じる子には良い刺激になりますが、「もっと静かに勉強したい」「キャラに話しかけられたくない」と思う子にとっては、かえってストレスになることがあります。
すべての子どもに好かれるキャラクターというのは難しいものなので、この点は親子で実際に見て判断する必要があるでしょう。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
思春期の子どもにとって、アニメキャラが頻繁に登場する教材は、「子どもっぽい」「バカにされている気がする」といった抵抗感につながることがあります。
すららは丁寧で親しみやすい解説を意識して作られていますが、かえってそれが「うるさい」「無理やり楽しませようとしてくる」と思われることもあるのです。
子どもによっては、それが原因で教材自体に拒否感を抱いてしまうこともあるので、特に中学生以上で導入する場合は、体験授業などで相性を確かめるのが安心です。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららは資料請求や無料体験をした後に、コールセンターやメールによるフォローが入ることがあります。
この連絡は「続けられそうですか?」「サポートのご案内です」といった親切な内容が多いですが、人によっては「何度も連絡が来るのは苦手」「押し売りっぽく感じる」と受け取られることもあります。
営業スタイルは比較的ソフトですが、SNSや口コミの中では「電話が多い」「LINEが来すぎる」といった声が投稿されていることもあり、勧誘の印象が残ってしまう人もいるようです。
過去に他の通信教材でしつこい勧誘を経験している家庭ほど、敏感に反応してしまう傾向があります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
LINEやメール、電話でのフォローは、基本的には丁寧で誠実なものですが、頻度が高すぎると「監視されているみたい」「干渉が強すぎる」と感じる家庭もあります。
SNSでは一部の体験者が「連絡多すぎてうざい」「営業電話っぽい」と投稿している例もあり、それが拡散されることで「すらら=うざい」というイメージが一人歩きしてしまうこともあります。
実際には希望すれば連絡頻度を減らすことも可能なので、最初の段階で相談しておくと安心です。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは1教科ごとではなく、全教科使い放題というメリットがありますが、月額料金は決して安い方ではありません。
教材の質やコーチサポートの手厚さを考えれば妥当な価格ですが、子どもが継続して取り組まない場合や、学習の成果が見えづらいときには、「高いだけで効果がない」と感じてしまう保護者もいます。
特に、親が期待して「これで変わるはず」と思って導入したのに、子どもがやる気を出さない場合には、「こんなに払ってるのに…」という不満が募りやすくなります。
効果が見えない期間が長いと、評価も厳しくなりがちです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは無学年式で自分のペースで進められるのが魅力ですが、言い換えれば「自分で取り組まなければ進まない教材」でもあります。
そのため、保護者のサポートが一定期間必要になることもあり、「放っておいても勝手にやってくれる」という期待とは少し違った印象を受ける場合があります。
最初は声かけや伴走が必要で、そこでつまずくと「料金のわりに効果がない」「もっと楽に進められる教材の方がよかった」と思われてしまうこともあるようです。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
すららの評判を調べる中で「料金が高いのでは?」という声を見かけることがあります。
確かに、月額数百円で使える教材と比べると、すららはやや割高に感じるかもしれません。
しかしその分、無学年式の自由度や発達障害・不登校対応といった手厚いサポート体制、そしてプロのすららコーチによる個別の学習フォローなど、他の家庭用教材にはないメリットが数多く用意されています。
さらに、1つの契約で兄弟姉妹も一緒に使える仕組みになっているため、家庭によってはコストパフォーマンスが非常に高くなるケースもあります。
今回は、そんなすららの料金プランの中でも「入学金」に焦点を当ててご紹介します。
初めての方が知っておきたい基本的な費用感を、表とともに解説していきます。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを始める際に必要な初期費用として、「入学金」が設定されています。
これは、コースによって金額が異なっており、選ぶ内容によって差があるのが特徴です。
すららでは、小中・中高5教科コースと、小中・中高3教科、小学4教科コースの2つのパターンがあり、前者は7,700円(税込)、後者は11,000円(税込)となっています。
一見すると「高いかな?」と感じる方もいるかもしれませんが、この入学金にはコーチによる初期カウンセリングや学習設計、すららシステムの個別最適化など、開始時に必要なサポートが含まれています。
子ども一人ひとりに合わせた細やかなスタートを切るための大事な投資だと考えると、納得感のある金額と言えます。
以下の表で、入学金の金額をコース別に確認できます。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの家庭用タブレット教材では、必要に応じて教科数を選べるのが特長のひとつです。
特に3教科(国語・数学・英語)に対応したコースは、学習の基礎をしっかり固めたいご家庭に人気があります。
このコースは、通常の「毎月支払いコース」と、少し割安になる「4ヵ月継続コース」の2種類の料金プランが用意されています。
毎月支払いコースでは月額8,800円、4ヵ月継続コースでは1ヵ月あたり8,228円となっており、継続の意思がある方には後者の方が経済的です。
いずれのコースも、無学年式・AIサポート・記述力を伸ばす設計といった、すららの機能はフルに使えるため、教材内容での差はありません。
お子さまのペースに合わせた学びと、保護者の負担軽減を両立させたい方におすすめです。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
理科・社会も含めた4教科コースは、「主要科目はすべて網羅したい」「教科書に近い内容をまんべんなく学びたい」というご家庭にぴったりのプランです。
特に中学受験や定期テスト対策を意識したご家庭では、この4教科コースを選ばれるケースが増えています。
毎月支払いでの料金は8,800円と、3教科コースと同額でありながら理科・社会が追加されるため、コスパが非常に高いといえます。
さらに、4ヵ月継続コースでは月額が8,228円に抑えられ、よりお得に継続学習が可能です。
特にすららの理社は、図解やイラスト、対話形式での導入など、理解しづらい用語や流れを丁寧に説明してくれるため、「暗記が苦手」という子でも安心して学ぶことができる設計になっています。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科すべてをカバーするこのコースは、すららの中でも最も内容が充実したプランです。
英語を含めた全科目を一貫して学ぶことができるため、苦手な教科の取りこぼしをなくし、バランスよく学力を伸ばすのに最適な選択です。
英語はリスニング・リーディングに加えてスピーキングの訓練も含まれており、4技能型の学習ができるのが特長です。
毎月支払いコースの月額は10,978円となっており、全教科対応としては妥当な価格帯です。
さらに、4ヵ月継続コースを選ぶと、月額10,428円に抑えられ、長期的な利用を考えているご家庭にはお得です。
すららは1契約で兄弟利用も可能なので、複数人での利用を検討している方にとっても、5教科コースは費用対効果の高いプランです。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
「すらら うざい」というワードを見かけると少し心配になる方もいるかもしれませんが、実際の利用者の声を見ていくと、「教材の広告が頻繁に出てくる」「親に勧められて嫌だった」など、教材そのものの質というよりは周辺の要因による印象が多いのが実情です。
本来の「すらら」は、特に勉強のつまずきや学習習慣の定着に悩む子どもたちに寄り添う設計がなされており、他の家庭用教材とは一線を画す内容になっています。
ここでは、特に人気のある「国語・算数(数学)・英語」の3教科コースに焦点をあてて、勉強効率や学習効果、実際の学びの流れについて詳しく紹介していきます。
すららがどんな学習成果をもたらすのか、利用を検討している方にはきっと参考になるはずです。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースは、小学生から中学生、高校生までを対象に、国語・算数(数学)・英語の主要教科を網羅しています。
中でも注目すべきなのは、「つまずきやすいポイント」にAIが着目し、一人ひとりに合ったカリキュラムを自動で調整してくれることです。
これにより、理解できていない部分に戻って復習しながら、着実に基礎から応用へと学習を進められる流れが自然と構築されます。
特に中学生にとっては、内申点に直結する主要3教科をしっかり伸ばせる仕組みが整っているため、定期テストの点数アップにもつながりやすいです。
すららは、ただ教科書をなぞるだけでなく、「できた!」「わかった!」という小さな成功体験を積み上げることで、学習への前向きな姿勢を引き出してくれる教材です。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららでは、授業が一方通行ではなく、アニメキャラと会話をしながら学ぶ「対話型」のスタイルになっており、インプットとアウトプットが自然と繰り返される構成になっています。
そのため、ただ動画を眺めるだけの受け身の学習にならず、自分の頭で考えながら進めることができ、基礎の理解がとても早く定着します。
特に算数や英語など、基礎の積み重ねが必要な教科においては、最初の「理解の深さ」が後の応用力に直結するため、こうした構造は非常に効果的です。
従来の紙教材や動画授業では飽きてしまうような子でも、すららのような双方向型なら興味を保ちながら学習を継続しやすいです。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららは、1回の学習が10〜15分程度と短めに区切られており、集中力が続きにくい子どもでも取り組みやすいよう工夫されています。
しかも、その短時間の中で、「問題を解く」→「なぜその答えになるのかを説明」→「似た問題で応用」のサイクルがしっかり組まれており、ただ正解するだけでは終わらない深い理解を促してくれます。
特に、わかったつもりになりやすい文法問題や読解問題では、なぜ間違えたのかをアニメーション付きで振り返ることができ、子ども自身が納得しながら学習を進められます。
こうした構造により、学んだことを実生活やテスト問題に応用する力が自然と身につくようになっているのです。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって、内申点は高校受験に直結する非常に重要な評価指標です。
そして、その内申点の大部分は国語・数学・英語の3教科に強く影響されるため、これらを集中的に対策することが成績向上に直結します。
すららの3教科コースでは、定期テストの出題傾向に合わせた演習問題や、つまずきやすいポイントの再解説などが充実しており、「なんとなく分かっていた」を「しっかり得点できる」状態まで引き上げてくれます。
また、成績が上がることで自信がつき、学習意欲そのものが高まる好循環も生まれやすくなります。
「点数を上げたい」「内申を上げたい」と思っている中学生には、特におすすめのコース内容になっています。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
すららの4教科コースでは、理科と社会の学習において「繰り返し学習」と「確認テスト」が非常に効果的に組み込まれています。
特に理科や社会のように暗記が必要な教科は、ただ覚えるだけではすぐに忘れてしまいがちですが、すららは講義の後にタイミングよく確認テストが用意されており、インプットとアウトプットをセットで行える仕組みが特徴です。
しかもそのテストはAIが内容を最適化してくれるため、本人の理解度に合わせて自然と繰り返すように設計されています。
定着を重視した構成になっているため、復習の時間をあらためて取らなくても、毎日の学習の中で自然に知識が積み重なっていくのが魅力です。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららの授業は、長々とした解説ではなく「ポイントを絞った要点学習」に特化しているため、限られた時間でも効率よく学習を進められるという強みがあります。
特に理科や社会といった教科は、内容が広く、細かな暗記ポイントが多いため、何から手をつけてよいか迷いがちですが、すららではその心配がありません。
授業の中で「ここが重要」「テストに出やすい部分」という情報を明確に教えてくれるので、自然と力を入れるべき箇所がわかり、時間の使い方に無駄がないのです。
部活や習い事で忙しい子どもでも、短時間で成果を出したいと考えているご家庭にはぴったりな学習スタイルだと感じます。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
すららは、学校の授業や一般的な塾よりも「短時間で理解→演習→定着」まで進められる点が大きな特長です。
講義内容は映像とナビゲーションを使って視覚的・聴覚的に理解を促してくれるため、教科書を読むよりもはるかに頭に入りやすい構成です。
また、すぐに確認問題が出題されるため、その場で理解度を測ることができ、自分がどこを間違えたかも明確にわかります。
これにより、「理解したつもり」のままテスト本番を迎えてしまうリスクを減らすことができます。
塾よりも短時間で効率よく勉強したい、というニーズに応えられる教材設計になっているのが、すららの強みです。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
すららの5教科コースでは、国語・数学・英語・理科・社会の全てをカバーしており、学校のテスト対策や内申点アップを目指す中学生にとって非常に有効な学習方法となっています。
特に中学生では、高校受験において内申点の重要性が高いため、「苦手教科がある」「3教科だけ頑張っている」という状態では不利になることがあります。
その点、すららはどの教科も無学年式で自由に学べるため、苦手を後回しにすることなく、満遍なく取り組めるのが魅力です。
全体的なバランスをとりながら学習することで、通知表の評価にも直結しやすく、基礎から応用まで無理なくカバーできる点で、安心して使える教材です。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる
すららの5教科コースは、高校受験にも直結する実力をしっかりと育てることができる内容になっています。
基礎力の養成だけでなく、応用問題や記述式の問題にも段階的に取り組める構成になっており、実際の模試や過去問対策としても活用できる力が身につきます。
また、各教科の単元ごとに理解度をチェックし、弱点をその場で補える設計になっているため、「やりっぱなし」で終わらず、本番に強い学力をしっかりと育ててくれます。
受験前になってから焦るのではなく、日頃から5教科すべてをバランスよく鍛えておけるので、内申点だけでなく学力試験への対応力も自然と高めることができます。
勉強効果3・ 5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららの大きな特徴は、AIによる個別最適化された学習サポートです。
5教科すべての学習履歴をAIが分析し、どの単元が苦手なのか、どのタイミングで復習すべきかを自動で提案してくれます。
これにより、子ども自身が「何をやればいいかわからない」と迷うことなく、効率的に学習を進めることができます。
学校の授業の進度や、塾の宿題に追われることなく、まさに自分のペースで着実に力をつけていける点が魅力です。
自分専用の学習計画がいつでも反映されるため、日々の勉強に無駄がなく、短時間でもしっかりと成果が出るよう工夫されています。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
すららの利用者から多く聞かれるのが、「時間の割に効果が高い」という声です。
塾や他の教材では、通塾時間や準備の時間など、勉強以外に使われる時間も多くなりがちですが、すららはすべてオンラインで完結するため、時間を無駄にせず集中して学習に取り組めます。
また、わかりやすい講義と即時の問題演習の流れにより、知識の吸収率も高く、短い時間でも確実に力がついていることを実感しやすいです。
時間あたりの学習効率を重視する家庭には、コストパフォーマンスの面でも非常に優れた教材だといえます。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
家庭用タブレット教材「すらら」は、ネット上では一部で「うざい」といった検索ワードが見られることもありますが、それは広告の頻度や親子のすれ違いに関する誤解が主な原因です。
実際には、不登校や発達障害を持つお子さんにも非常に評価されている教材であり、無学年式や対話型アニメーション授業、すららコーチの個別サポートなど、多くの安心材料が揃っています。
学校の集団授業では難しい「個別に合わせた学習」ができるのがすららの大きな強みで、プレッシャーなく取り組める環境が整っているため、学習に対して苦手意識のある子どもでも自然にステップアップしていけるのが特長です。
ここでは、そんなすららが「安心・安全に使える理由」について、具体的にご紹介していきます。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららは「無学年式」の教材なので、学年にとらわれず、子どもの理解度やコンディションに合わせて自由に学習を進めることができます。
これは、発達障害のあるお子さんや、学校に行けないことで「勉強が遅れているかも…」と不安になっている子にとって、大きな安心感につながります。
学校のように周りと同じペースで進む必要がなく、「今日は調子がいいからたくさん進めよう」「今日はゆっくりやろう」といったように、自分のペースを尊重できる仕組みになっています。
プレッシャーや比較から解放されることで、「やらされてる勉強」ではなく、「自分で進める勉強」に変わり、主体的に取り組む気持ちが芽生えていきます。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
学校ではクラス全体の進度に合わせなければならず、少しつまずいてしまうと「置いていかれる」という焦りが出てしまうこともあります。
逆に、理解が早くても先に進めないもどかしさを感じる子もいます。
すららではそういった「集団のペース」に合わせる必要がないため、子ども自身のペースで落ち着いて取り組むことができます。
これにより、学習が苦手な子も得意な子も、それぞれにとって最適なスピードで進められるため、無理なく継続しやすいのが魅力です。
学びに対するストレスが少ない環境をつくることで、子どもが前向きに学習と向き合えるようになります。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害のあるお子さんの学習スタイルは一人ひとり異なります。
たとえばADHDタイプの子は集中力が持続しにくい一方、スイッチが入ると一気に集中できる特性があります。
すららは時間帯や量を自由に調整できるため、こういった「集中できるタイミング」を逃さず学習に活かせます。
また、ASDタイプの子はルーティンを大切にする傾向があるため、毎日決まった時間に取り組むことで安心感を持って学習を継続できます。
すららはこうした多様な学習特性に柔軟に対応できる設計になっているため、子どもが「自分らしく学べる」教材として、多くの家庭で重宝されています。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
すららのもうひとつの安心ポイントは、すべての学習が「非対面」で完結できるという点です。
特に人との関わりに不安を感じやすいお子さんや、不登校の経験がある子にとっては、対面での指導やコミュニケーションが大きなストレスになってしまうことがあります。
すららはアニメーションのキャラクターが優しく教えてくれるスタイルなので、表情や声のトーンに敏感な子でも安心して受け入れることができます。
また、間違えても怒られることがなく、ポジティブなフィードバックが中心なので、学習への抵抗感がぐっと減るのも特徴です。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
人とのやりとりが苦手な子にとって、「感情の起伏」や「表情の変化」がある相手と接するのは緊張の原因になります。
でも、すららのキャラクターは常に穏やかで一定のテンポで話しかけてくれるため、不安を感じることがありません。
たとえ間違えても、「こういう理由でこうなるんだよ」とやさしく説明してくれるだけなので、怒られる心配もなく、安心してチャレンジできるのです。
子どもが失敗を恐れずに取り組める環境が整っているからこそ、「もっとやってみよう」という気持ちが育ちやすくなります。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
学校や塾では、どうしても先生やクラスメイトとのやりとりが発生します。
それがストレスになって学習に集中できないというケースも多く見られます。
すららでは、そうした対人コミュニケーションを必要とせず、自分だけのペースで、自分だけの空間で学習を進められます。
特に、他人の視線や評価を気にしやすいお子さんにとって、この「ひとりでも安心して取り組める環境」は非常に大きな意味を持ちます。
安心感のある環境だからこそ、学ぶ意欲が自然と湧いてくるのです。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは「すべての子どもが安心して学べること」を目指し、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて設計されています。
これは、特定の発達障害や学習障害の有無にかかわらず、誰もが「理解しやすく」「つまずきにくい」構造にすることで、より多くの子どもたちに適した学習体験を提供できるという考え方です。
特に、読字障害(ディスレクシア)や、言語理解に時間がかかるASD(自閉スペクトラム症)傾向の子どもにもわかりやすい内容となっており、「聞いて理解する」「見て理解する」両方のアプローチが備わっています。
また、音声のスピードを子どものペースに合わせて調整できる機能もあるため、早口が苦手な子には「ゆっくり再生」、集中力が続かない子には「テンポよく進む」など、個別の特性に配慮した環境を整えることができます。
こうした設計によって、発達障害のあるお子さんでも「わからない」「ついていけない」というストレスを感じにくく、自分のペースで安心して学べるのがすららの強みです。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららは「子どものつまずきに気づき、寄り添う」ことを大切に設計されています。
難しい表現を避けたり、ひとつの説明に対して視覚・聴覚両方でアプローチをしたりすることで、どんな子どもでも「わかった!」を実感しやすくなっています。
学年や年齢、個別の特性に関係なく学べる環境が整っているからこそ、多くの家庭で選ばれているのです。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
すららの設計は、読むことが苦手なディスレクシアの子や、言語処理に時間がかかるASDの子にも優しいつくりになっています。
文章を読むだけでなく、音声読み上げや図解が豊富に使われており、内容を「聞いて理解する」ことができるため、読むスピードや読解力に不安があるお子さんでも、スムーズに内容を吸収できます。
説明の繰り返しも多く、自然に定着を促す構成も魅力です。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
すららは、学習スタイルに合わせた情報提供ができる教材としても評価されています。
視覚から情報を捉えるのが得意な子には、イラストや図解を多く取り入れたスライドが用意されており、耳から学ぶのが得意な子には、ナレーション付きの解説が効果的です。
このように、どちらのタイプにも対応できる柔軟性があることで、学習が「楽しい」と思える時間に変わるのです。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
学習中の音声スピードを自由に調整できるのは、すららの大きな魅力のひとつです。
話すスピードが速いと集中できなかったり、逆に遅いと退屈に感じてしまったりする子どもも多いため、音声速度を自分に合ったペースに調整できるのは非常に実用的です。
「もう一度ゆっくり聞きたい」「テンポよく復習したい」といったニーズに合わせて、ストレスなく学習が進められる環境を整えられる点が、発達特性に配慮した安心設計と言えます。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
子どもにとって「間違えること」は決して悪いことではありませんが、実際には間違えることで恥ずかしい思いをしたり、自信をなくしてしまったりするケースが少なくありません。
特に学校や塾のような「人の目」がある環境では、間違いを恐れて積極的に発言できない子も多いのが現実です。
すららはそういった心理的なハードルを取り除くことを大切にしており、「間違えても大丈夫」「やり直していいんだよ」という前向きな姿勢で学べるように設計されています。
問題を間違えたときも、否定するのではなく、自然と納得できるような解説を提示してくれるため、子ども自身が「次こそは理解したい」「もう一度やってみよう」と思える環境を整えてくれます。
このように、精神的な安心感を得ながら学べる仕組みが、すららの「安全設計」の根底にあるといえます。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららでは、「なぜ間違ったのか」を優しく丁寧に説明するスタイルが採用されており、子どもが自分で気づき、納得して学べるように工夫されています。
そのため、間違えても落ち込まず、むしろ「次はできるかもしれない」という前向きな気持ちを育てることができます。
これにより、自己肯定感を保ちながら学習を続けることができるのです。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
教室での学習は、他の子と比べられる環境でもあります。
その中で「できなかった」「間違えた」という体験は、子どもにとって大きなストレスになります。
しかし、すららは自宅で一人で取り組める上、誰かに見られることがないため、「失敗しても恥ずかしくない」と感じられる安心感があります。
これが、子どもが継続して学習に取り組める心理的な土台となっているのです。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららは、アニメキャラクターと一緒に学ぶ対話型の授業スタイルを採用していて、まるでゲームをプレイしているかのような感覚で学習を進められるのが魅力です。
学習内容そのものはしっかりとしたカリキュラムに基づいていますが、クイズ形式で進んだり、キャラクターからのリアクションがあったりと、「もう少しやってみたい」と思えるような工夫が随所にちりばめられています。
特にADHD傾向のあるお子さんにとっては、「すぐに褒められる」「すぐに達成感を味わえる」設計が、やる気の維持につながりやすいです。
こうした即時性のあるフィードバックは、集中力に波がある子にとって非常に重要であり、「続けられる自信」を少しずつ積み重ねる手助けをしてくれます。
親が声をかけなくても、自然と学習が進む設計は、保護者にとっても安心材料のひとつです。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららの授業は、ただ文字と動画で解説するのではなく、キャラクターが出てきて「この問題どう思う?」と問いかけてくれたり、答えに対してリアクションを返してくれたりするため、子どもが自然と会話に参加しているような気持ちになります。
そのうえで、問題に正解すればすぐに褒めてもらえたり、成績がグラフで可視化されたりと、達成感を感じられる設計になっており、モチベーションを保ちやすい仕組みが整っています。
これが、「もう一問やってみようかな」という気持ちにつながり、継続的な学習に結びつく大きな要因となっています。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHDの特性として、長期的な目標よりも「すぐに成果が見えること」に反応しやすいという傾向があります。
すららは、この特性を理解したうえで、「問題に答えるとすぐにフィードバックが返ってくる」「成績がすぐにグラフ化される」など、即時性のある反応を重視した設計がなされています。
これにより、達成感や承認感をその場で得ることができ、「やる気があるうちにどんどん進めたい」という気持ちを自然に引き出すことができます。
長く集中できないタイプのお子さんにとっても、テンポのよい構成が続けやすさにつながっているのです。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
すららには、子ども一人ひとりに寄り添った学習設計をしてくれる「すららコーチ」がついており、これが家庭学習を続ける上で非常に大きな安心感につながっています。
とくにADHDやASD、学習障害などの特性を持つお子さんに対して、理解のある対応ができるよう訓練されたコーチが多く在籍しているため、「どう進めていいかわからない」「親子で衝突してしまう」といった悩みを抱えずに済むケースが多いです。
保護者にとっても「一緒に見守ってくれる第三者がいる」ことで精神的な負担が大きく軽減されます。
教材を渡して終わりではなく、実際に日々の学習進度を管理してくれるプロの存在があることで、子どもに合った最適なペースで学習が進められるようになります。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららのコーチは、発達障害に関する知識や、学習支援に関するノウハウをしっかりと持っている方が多く在籍しています。
そのため、集中力が続かない、感情の起伏が激しい、学習の偏りがあるといった子どもたちにも、それぞれの性格や特性に寄り添った声かけや対応ができるのです。
親が一人で悩みを抱えることなく、コーチと二人三脚で学習を見守れることで、家庭内のストレスも大幅に減らすことができます。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
すららコーチの役割は、単なる見守りだけではありません。
コーチは、子どもの理解度や学習履歴を見ながら、次にどの単元に進むべきか、どこでつまずいているのかを分析し、それに応じた学習計画を提案してくれます。
さらに、必要に応じて保護者にフィードバックを行い、学習への取り組みを支えるためのアドバイスもくれます。
「ただのサポート役」ではなく、「学習の伴走者」として、長期的に子どもの成長を支えてくれる存在です。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららの最大の安心材料のひとつが、「完全オンライン」で学習が完結するという点です。
塾に通わせる必要がなく、タブレットやパソコン1台あれば、すべての学習が自宅で完了します。
これは、外出が難しいお子さんや、家庭の事情で通塾が難しいご家庭にとっては大きなメリットです。
また、天候や体調に左右されず、毎日安定して学習を続けられるため、「今日は無理だからやめよう」といった中断を防ぐことができます。
親にとっても送り迎えの手間や、通塾時の安全確認の負担がないため、心の余裕が生まれやすくなります。
勉強の場が「家」という安心できる空間であることは、特に繊細なお子さんにとって非常に大切なポイントです。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららの学習に必要なのは、インターネット環境と1台のデバイスだけ。
専用の端末や高価な教材を買い揃える必要はなく、すでに家庭にあるタブレットやパソコンでスタートできる点が魅力です。
また、教材が届くのを待ったり、毎回の予習復習の準備をしたりする必要もなく、ログインすればすぐにその日の学習が始められるので、親の手間が最小限で済みます。
とくに共働き家庭や、下の子がいるご家庭では、「勉強は任せておけばOK」という仕組みがとても助かる存在になります。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
体調不良や不登校、あるいは一時的な入院などで学校に通えない期間があったとしても、すららがあればその間の学習を家でカバーすることができます。
学校と同じペースで進める必要はなく、子どもの体調や気分に合わせて柔軟に学習を調整できるため、「勉強が遅れてしまった」と焦る必要もありません。
自分のペースで進めながらも、確実に理解を深めていけるため、再び学校に戻るときも「ちゃんとやってたから大丈夫」と思える自信につながります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは、発達障害や不登校のお子さんにも対応した無学年式の家庭学習教材として高い人気を集めていますが、中には「もう使わないからやめたい」「合わなかったので解約したい」と思うご家庭もあります。
ただし、実際に解約や退会を進めようとしたときに、「方法が分かりにくい」「ネットから手続きできないの?」と戸惑うケースもあるようです。
すららでは、解約や退会について明確なルールが定められており、正しい手順を知っておくことでスムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、すららの「解約」と「退会」の違いをはじめ、実際の解約方法や注意点について詳しくご紹介していきます。
特に「電話しか受け付けていない」といったポイントは、あらかじめ知っておくと安心です。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめたいと考えたとき、「退会」と「解約」の違いを理解していないと、手続きが中途半端になってしまうことがあります。
すららの「解約」とは、月額料金の支払いを停止し、教材の利用をストップする手続きのことを指します。
これを行えば、それ以降は請求が発生しません。
一方で「退会」とは、すららの会員情報そのものを削除し、アカウントや学習履歴などもすべて消えてしまう操作です。
つまり、利用を終了するためには、まず「解約」を行い、必要があれば追加で「退会」を申請するという流れになります。
うっかり退会だけしてしまうと、月額料金が継続されてしまう可能性があるので注意が必要です。
まずは「解約」が先、その後に「退会」という順番を覚えておきましょう。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
すららの「解約」とは、有料コースの月額利用を停止するための正式な手続きのことです。
学習自体は続けず、支払いを止めたい場合には、まずこの解約を済ませなければなりません。
ここで注意すべきは、解約の手続きをしないままアプリやサイトの利用をやめただけでは、月額料金は継続して請求されてしまうという点です。
「使っていない=自動的に解約される」と勘違いしないようにしましょう。
解約手続きをきちんと行うことで、その時点から課金は止まり、次回以降の請求も発生しなくなります。
すららではこの解約を電話でのみ受け付けており、利用停止を希望する場合には、後述する「すららコール」への連絡が必要となります。
すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
「退会」とは、すららのシステム上からアカウント情報そのものを削除する手続きのことを指します。
この操作を行うと、これまでの学習履歴・診断結果・成績レポートなどのすべての情報が削除され、ログインもできなくなります。
つまり、完全に「会員ではなくなる」状態になります。
解約とは異なり、退会は学習やデータの復元ができなくなるため、「また使うかもしれない」「一時的に休会したい」といった場合には、退会ではなく解約だけにとどめておくのが安心です。
すららでは解約が済んでいれば、料金は発生しませんので、退会はあくまで「アカウントを完全に削除したいとき」にだけ行うオプション的な位置づけになっています。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約手続きは、公式サポートである「すららコール」への電話によってのみ受け付けられています。
メールやWEBフォームでは手続きを完了できないため、解約を希望する場合には必ず電話をかける必要があります。
少し手間に感じるかもしれませんが、本人確認をきちんと行った上で手続きできるため、間違いやトラブルを防ぐ意味でもこの方法が採られています。
電話は平日の10時〜20時に対応しており、土日祝は受付時間外となります。
学校や仕事の合間に電話できる時間を見つけておくとスムーズです。
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約については、公式に「メールやWEBからの手続きは一切受け付けていない」と明言されています。
そのため、「お問い合わせフォームから連絡しておけばOK」と思って放置してしまうと、月額料金が継続して発生してしまう恐れがあります。
解約したいときは、必ず上記の「すららコール」へ電話をかけることが必要です。
電話での本人確認が済んでから初めて、正式な解約として受理される仕組みになっているため、確実な処理を希望する方はこの点を忘れずに押さえておくことが大切です。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
すららの解約手続きでは、電話をかけた際にいくつかの本人確認情報を求められます。
たとえば、登録者の名前や生徒ID、登録時の電話番号などが必要になるケースが多いため、事前に用意しておくとスムーズに進みます。
これはセキュリティ上の理由でもあり、契約者以外が勝手に手続きを進められないようにするためです。
また、解約にあたっての注意事項や確認事項も電話でしっかり説明されるため、「言った言わない」のトラブルも起こりにくいのが安心ポイントです。
とくに、支払日や更新タイミングによっては最後の引き落としがあるケースもあるので、その点についても必ず確認しておきましょう。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約手続きを進める際には、「いつから利用を停止したいか」を電話で伝える必要があります。
ただし、すららでは月の途中で解約しても日割り計算は行われない仕組みになっているため、どの日に解約してもその月の利用料は満額請求される点に注意が必要です。
たとえば、月初に解約しても、その月いっぱいはサービスが利用でき、料金も1か月分が発生します。
ですので、月末ぎりぎりよりも、次の更新日前に余裕をもって解約するのが安心です。
解約の希望日を伝える際には、この日割り制度がない点を理解したうえでタイミングを選ぶようにしましょう。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを完全にやめたい場合には、解約手続きが完了したあとで「退会」も申し出ることができます。
退会を希望する場合は、解約の電話の際にそのまま「退会も希望します」と伝えれば対応してもらえます。
退会を行うと、学習履歴や成績などのデータはすべて削除されるため、「後から再開したい」という可能性がある方は退会せずにアカウントだけ残しておくことも可能です。
退会せずとも、解約していれば料金は一切かからないため、しばらく使わないけど様子を見たいという方は解約だけしておくという選択肢もあります。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
解約と同時に退会も済ませたい場合は、電話の際にオペレーターへ「退会も希望します」と伝えればOKです。
その場で手続きを進めてもらえるため、後日あらためて連絡する必要がありません。
退会が完了すると、登録情報や学習記録がすべて消去され、ログインもできなくなります。
もう利用する予定がない方や、個人情報を完全に削除しておきたい方にとっては安心の方法です。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららは、解約手続きが完了していれば、その後に退会をしなくても料金の請求は止まります。
ですので、「また使うかもしれない」「とりあえず様子を見たい」と思う場合には、退会せずに解約だけしておくというのも十分な選択肢です。
アカウントを残しておけば、再開したいときにまた手続きなしですぐ利用できます。
逆に、完全に利用を終了したい方は、退会まで行うことで個人情報や履歴が全て削除され、すっきりした状態になります。
状況に合わせて、どちらかを選ぶとよいでしょう。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、「うざい」という声が一部にある反面、実際に使ってみると「思ったより楽しい」「学びやすい」と感じるご家庭が多い教材です。
特にタブレット学習が初めてのお子さんにとっては、「どう使えば続くの?」「どうしたら効果が出るの?」といった疑問が出てくるものです。
すららは、学年に縛られない無学年式、キャラクターによる対話型授業、そして個別に寄り添ってくれる「すららコーチ」が大きな魅力ですが、せっかくの機能も正しく活用しないと、その良さが最大限に活かされないこともあります。
そこで今回は、小学生がすららをより効果的に使うためのコツや工夫について、実践的な視点からご紹介します。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生がすららを使うときは、「とにかくたくさんやらせよう」と無理をさせるよりも、「毎日少しずつ、楽しく続ける」ことが最大のポイントになります。
特に低学年のうちは、学習習慣をつけること自体が目標でもあり、「学ぶっておもしろいかも」と思わせることができれば、効果は自然とついてきます。
すららは無学年式なので、学年にこだわらず先取りも復習も自由にできますが、だからこそ子どものペースに合わせて無理のないリズムを作ることが大切です。
ここでは、実際のご家庭でもよく取り入れられている、小学生向けの「すらら活用術」を紹介していきます。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
すららを効果的に活用するための第一歩は、「短時間×高頻度」の習慣づくりです。
小学生、特に低学年のお子さんは集中力が長く続かないことも多いため、「一度にたくさんやらせる」よりも、「毎日ちょっとずつでも継続する」ことの方が学習効果は高くなります。
目安としては、1回あたり20〜30分、集中できる範囲で無理なく取り組むのが理想です。
このリズムが身につけば、「今日はやらなくちゃ」という義務感よりも、「今日はどこまでやろうかな」といった前向きな気持ちで取り組むようになり、学習が生活の中に自然と定着していきます。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
小学生は「達成感」や「成功体験」が継続のカギになります。
そこでおすすめなのが、ごほうび制度の活用です。
たとえば、1ユニット終わるごとにシールを貼る、カレンダーに印をつける、小さなおやつをご褒美にするなど、日常の中に小さな「達成の演出」を入れてみると、子どもは次も頑張ろうという気持ちになりやすいです。
重要なのは、ごほうびが大きなものでなくてもいいということです。
すららのキャラクターが褒めてくれることに加えて、親からのちょっとした「すごいね!」「がんばったね!」という声がけもごほうびの一つになります。
こうした積み重ねが、やる気を自然と引き出してくれるのです。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
低学年のうちは、子どもだけに任せるよりも、親がそばで一緒に楽しむ姿勢を見せることがとても大切です。
「すらら、今日は何やるの?」「一緒に見てもいい?」と声をかけるだけで、子どもは「自分のやってることに関心を持ってくれてる」と感じ、やる気がアップします。
特に最初のうちは、「一緒にやろう!」と誘いながら習慣をつけていくと、抵抗感が少なくスムーズに始められます。
親が関わるといっても、ずっと隣で見ている必要はありません。
最初の数分だけ付き合って、あとは見守るだけでも十分です。
学習を「家族の時間」として取り入れていくことが、長く続けるコツになります。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
子どもはどうしても「好きなこと」を優先しがちで、苦手な教科は後回しになりやすいです。
でも、すららにはAIによる「つまずき診断」機能があるので、苦手な分野や単元を客観的に把握することができます。
この機能を活用して、「苦手をひとつずつ攻略する」という視点で学習を始めると、成長の実感が得やすくなり、自然と自信もついてきます。
特に、最初に小さな苦手を克服できると「自分でもできた」という達成感が生まれ、それが次のモチベーションへとつながります。
好きな科目ばかりやって偏らないよう、バランスを見ながら取り組むことが効果的な使い方のポイントです。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、学習内容がぐっと難しくなり、定期テストや内申点といったプレッシャーも本格化してきます。
そんな中で、すららをどう活用するかによって、学習の成果が大きく変わってきます。
すららは「自宅で自分のペースで学べる」ことが最大の魅力ですが、ただ受け身で動画を見ているだけでは、やはり効果は半減してしまいます。
中学生にとって大切なのは、目的意識を持って使うことと、日々の学習習慣を無理なく継続することです。
すららのシステムには、定期テスト対策や予習復習、苦手克服、スケジュール管理までサポートできる機能が整っているため、ポイントを押さえて活用すれば、学校の勉強にも自信がついてくるはずです。
ここでは、すららを中学生がより効果的に使うための4つの方法をご紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
すららは、学校の定期テスト対策にも非常に相性が良い教材です。
単元ごとに用意されたまとめテストや理解度チェックを活用することで、テスト範囲に合わせた学習がしやすくなっています。
まずは学校から配られたテスト範囲表を見ながら、すららの学習単元と照らし合わせ、「どこまで学べば試験に間に合うか」を逆算して計画を立てましょう。
時間のない中学生にとっては、無駄のない効率的な学習が求められます。
すららなら、AIが進捗状況を記録し、苦手分野を優先的に出題してくれるため、自分で苦手を探す手間も省けます。
「テスト前だけ頑張る」のではなく、日頃からすららを使っておけば、焦らずにテスト本番を迎えることができます。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活動などで帰宅時間が遅くなりがちですが、その後の過ごし方が学習習慣のカギになります。
すららは自宅で好きな時間に取り組めるため、部活が終わってから寝るまでの1時間を「夜の学習タイム」として決めてしまうのがおすすめです。
タブレット学習は机に向かわずソファやベッドでもできるため、「ちょっと疲れていてもとりあえず開ける」というハードルの低さがあります。
この“始めやすさ”が継続のコツです。
また、夜にすららをやることで、「1日の学びの締め」としてのリズムができ、次の日の学校の授業にもつながりやすくなります。
毎日10分でも15分でも、続けることが力になるので、寝る前のルーティンとしてすららを取り入れると、学習ペースが安定します。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
中学生になると勉強の範囲も広くなり、自分ひとりではどこから手をつけたらいいかわからなくなることもあります。
そんなとき頼りになるのが「すららコーチ」の存在です。
すららコーチは、AIが分析したデータをもとに、子ども一人ひとりのつまづきポイントを見つけ、学習計画を一緒に立ててくれる心強い存在です。
「今週は何をどれだけやるべきか」「テストまでにどの単元を終わらせるか」といった具体的なアドバイスをもらえるため、目標が明確になります。
子ども自身だけでなく、保護者にもフィードバックが届くため、家庭での声かけにも役立ちます。
「勉強の相談相手がいる」ことで安心感が生まれ、やる気にもつながります。
コーチとのやり取りはすららの魅力のひとつなので、ぜひフル活用してみてください。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
すららの無学年式を活かすなら、「復習と予習」をバランスよく組み合わせるのが効果的です。
特に英語や数学のような積み上げ型の教科は、授業で「初めて見る内容」よりも、あらかじめすららでざっくりと予習しておくことで、学校の授業がより理解しやすくなります。
たとえば、英語ならbe動詞や過去形、疑問文などを動画で一度見ておけば、授業中に「あ、これ知ってる!」と感じられて、理解が深まりやすくなります。
一方で、テスト前や成績対策としては、すららのまとめテストや演習問題で復習もしっかり行い、苦手を確実に潰していくことが大切です。
予習で「先取り」、復習で「定着」というサイクルをうまく回すことで、学校の勉強と家庭学習がリンクし、成績アップにもつながります。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
すららは小中学生向けというイメージを持たれがちですが、高校生にとっても非常に効果的な学習ツールです。
特に「つまずきをそのままにしてきた」「授業のスピードについていけない」と感じている高校生には、無学年式で自分のペースで進められるすららが強い味方になります。
高校生になると、受験や模試など具体的な目標も出てくるため、「苦手をつぶす」「得意を伸ばす」のバランスが求められます。
すららでは、基礎の復習から共通テストの土台づくりまで幅広く対応しており、自宅学習を中心にした学力強化にぴったりの教材です。
ここでは、高校生がすららをどう活用すれば効果が高まるのか、そのポイントをご紹介していきます。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生の学習は、「できるところはどんどん進める」「つまずいた部分は戻ってやり直す」というスタイルが理想的です。
すららはまさにその使い方に適した無学年式で、苦手分野は小中の範囲まで戻って復習し、得意なところは応用問題や発展内容に挑戦できる柔軟性があります。
英語なら中学英語を総復習してから英文法の発展、数学なら因数分解や方程式に不安があれば基礎からやり直してもOKです。
自分で「ここが抜けている」と感じる単元を重点的にやることで、学力の底上げができるのがすららの大きな強みです。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校に進学すると、学校の授業が急に難しく感じたり、先生との相性が合わないという悩みを抱える生徒も少なくありません。
そんなときは、すららで「自分にとってちょうど良いペース」で学習を進めるのが効果的です。
授業では分からなかった内容も、すららのアニメーションと対話形式の解説で丁寧に復習できるため、「なんだ、こういうことだったのか」と理解がスムーズになることが多いです。
人と比べられることなく、自分のペースで安心して進められるという点は、ストレスの軽減にもつながり、高校生活全体の安定にも役立ちます。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生にとって避けて通れないのが模試や共通テストです。
すららは、こうした試験の土台となる基礎力をしっかりと固めるのに非常に有効です。
模試の結果を見て「基礎で落としている問題が多い」と感じた場合は、すららを使って中学や高校初期の単元からやり直すことが効果的です。
英語の文法ミスや数学の計算ミスなど、基本の理解が甘い部分をしっかり見直しておくことで、得点力がぐっと安定してきます。
すららは、暗記ではなく「理解して覚える」流れを大切にしているので、模試の応用問題にも対応しやすい思考力が育ちます。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生になると、勉強の計画や時間管理も自分でやらなければならない場面が増えてきます。
すららでは、学習時間や進度が自動的にグラフ化されて表示されるため、「今月はこれだけやった」「どこまで進んでいるか」が一目でわかります。
この「見える化」は、継続のモチベーションにもなりますし、保護者も進捗を共有しやすく、家庭での学習サポートにも役立ちます。
「今日は何をすればいいか」が画面に表示されるので、計画を立てるのが苦手な高校生でも安心して取り組むことができます。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校のお子さんにとって、学習だけでなく生活全体のリズムや自己肯定感の回復も大切な課題です。
すららは、そうした子どもたちに向けたサポート機能が豊富で、単なる教材ではなく「日常生活の中で安心して学べる環境」を整えてくれる存在でもあります。
家庭での学びを通じて、「学校には行けなくても勉強は続けられる」「少しずつ前に進んでいる」と感じることで、気持ちが落ち着き、自信が戻ってくる子も多いです。
ここでは、不登校の子どもたちにとってのすららの効果的な活用方法について紹介していきます。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
すららを不登校の学習支援に活用するうえで、まずおすすめしたいのが「生活リズムの再構築」です。
不登校の期間が長くなると、昼夜逆転や寝不足などの生活の乱れが生じやすく、それがさらなる心身の不調につながることもあります。
すららは1回の学習時間が短く設定されているため、「朝ごはんを食べたらすらら10分」というふうに、1日の中に小さな学習習慣を組み込みやすいのが魅力です。
これをベースに、「朝起きる→学ぶ→休む→また少しやる」といった生活リズムを整えていくことで、体内時計や気持ちが少しずつ回復していくことが期待できます。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
不登校の子どもが学習に向き合う際には、「誰にも見られず、自分のペースでできる」ことがとても重要です。
すららは、自宅で静かに自分だけの環境で取り組める教材なので、集団授業のプレッシャーが苦手な子でも安心して取り組めます。
アニメキャラクターと対話する形式の授業は、まるで一対一の授業を受けているような気持ちになれ、学習に対する不安や抵抗感を軽減してくれます。
「今日はこのくらいやってみよう」と自分の中で目標を立てながら進めることで、自信を少しずつ回復させることができます。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
すららには、正解したり、目標を達成したときに画面上でキャラクターが褒めてくれる「ほめ機能」があります。
これが、不登校や学習に自信を失っている子にとって非常に大きな励みになります。
「やればできた!」という体験は、ほんの小さなことでも自己肯定感を高めるきっかけになり、次への一歩につながります。
学校に行けないことで落ち込んでいる子どもに、「自分にもできることがある」と思わせてくれる、そんな優しい後押しがすららにはあります。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもが抱える悩みの一つに、「誰にも相談できない孤独感」があります。
そんなときにすららコーチの存在はとても心強いです。
すららコーチは、親ではない「第三者」として、やさしくフラットに子どもの話を聞いてくれたり、「こんなふうに頑張ってるよ」と声をかけてくれたりします。
親に言えないことも、コーチには言えることがあります。
コーチとのやりとりがあるだけで、「一人じゃない」「ちゃんと見守ってくれている人がいる」と思えるようになり、安心感が得られるのです。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
最近、「すららはうざい」という口コミを耳にすることがありますが、このような意見が出てくる背景にはいくつかの理由が考えられます。
まず第一に、個人の好みや生活環境によって感じ方が異なることが挙げられます。
また、使い方や使っている状況によっても、「うざい」と感じることがあるかもしれません。
さらに、情報過多やストレスの影響も考慮する必要があります。
一方で、すららは多くの人にとって便利で役に立つアプリケーションです。
例えば、手軽に予定を管理したり、タスクを整理したりするのに重宝されています。
そのため、「うざい」と感じる人もいれば、必須アイテムとして捉える人もいるのが現状です。
このように、人それぞれの視点や状況によって感じ方が異なることを踏まえ、他者の意見も尊重することが大切です。
自分にとってのメリットやデメリットをよく考えた上で、すららの活用方法を見直してみることも一つの方法かもしれません。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すらら(Slala)は、発達障害を抱える方々のための教育プラットフォームとして、高い評価を受けています。
すららの発達障害コースは、そのような方々が学びやすい環境を提供し、専門的なサポートを提供しています。
このコースの料金プランについてご案内いたします。
すららの発達障害コースには、月額制のプランがございます。
このプランでは、定額の料金を支払うことで、コース内の全てのコンテンツにアクセスできます。
さらに、専門家によるサポートも含まれており、受講者が安心して学ぶことができる環境を整えています。
料金プランには、さまざまなオプションがございます。
月額プランの他に、単発でのコース購入も可能です。
また、スペシャルコンテンツやワークショップに参加するための追加料金が必要な場合もございます。
料金プランの詳細については、すららのウェブサイトをご確認ください。
発達障害を抱える方々が、自分のペースで学び成長できるように、すららは柔軟な料金プランを提供しております。
このコースは、支援や理解が必要な方々にとって、有益な学習体験を提供することを目的としています。
料金プランに関する疑問やご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
当記事では、すららのタブレット学習が不登校の子供にとって出席扱いとなるかについて考察します。
不登校は教育における重要な問題であり、その解決策は慎重に検討される必要があります。
すららのタブレット学習は、不登校の子供たちにとって有益な教育手段となる可能性がある一方、出席扱いにまで及ぶかどうかは、個々の学校や地域の方針による部分もあります。
不登校の子供たちがすららのタブレット学習を利用する場合、その学習は実際の教室での出席と同様に扱われるかどうかは、学校側や教育機関のポリシーや指針によって異なります。
通常、学校は学生の出席状況を記録し、その出席率を評価の一環として活用しています。
従って、不登校の子供がすららのタブレット学習を通じて授業内容を学ぶ場合でも、その出席扱いについては学校や教育機関との相談が必要です。
すららのタブレット学習が不登校の子供たちにとって有益な教育手段であることは間違いありません。
柔軟性や個別指導が可能な点から、不登校の子供たちにとっては教育上の貴重な支援となることでしょう。
しかしながら、出席扱いに関しては、それがどのように認識されるかは地域や学校によって異なるため、具体的なケースにおいては専門家や関係者との相談が不可欠です。
最終的には、不登校の子供たちにとって最適な教育環境を整えるためには、教育関係者や保護者、学生自身が協力し合い、適切な解決策を模索していくことが肝要です。
すららのタブレット学習を活用しつつ、出席扱いに関する課題についても、対話と協力を大切にしていくことが望ましいでしょう。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社のキャンペーンコードを使用する際の手順についてご説明いたします。
まず最初に、お客様が商品を購入する際に、買い物カゴに商品を追加してください。
次に、お支払い画面で「キャンペーンコードを入力する」ボタンを選択してください。
そこに、お受け取りいただいたキャンペーンコードを入力していただくことで、割引や特典が適用されます。
キャンペーンコードは、お客様に特典をお楽しみいただくためのものですので、お見逃しなくご利用ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ますますご利用いただけることを願っております。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
「すらら」の会員である皆様、退会をご検討中の方々へ、退会方法について丁寧にご案内いたします。
退会手続きは簡単な手順で行うことができます。
まずは、退会をご希望の方はログイン後、マイページにお進みください。
そこで、「アカウント設定」または「会員情報」などのタブを開き、退会手続きを開始することができます。
退会手続きの際には、ご登録いただいた情報や退会理由をお伺いする場合がございます。
お手数おかけいたしますが、正確に記入いただきますようお願い申し上げます。
退会手続きが完了すると、会員資格が無効となり、すららのサービスをご利用いただけなくなります。
何かご不明点がございましたら、遠慮なくカスタマーサポートまでお問い合わせください。
退会に際しましては、今までのご愛顧に心より感謝申し上げます。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららを利用する際に基本的にかかる費用は、入会時に必要な「入会金」と、毎月支払う「受講料(コース料金)」の2つのみです。
教材の購入費やシステム利用料といった追加の料金は一切かかりません。
すららは紙の教材を使用せず、すべてオンライン上で学習が完結する仕組みとなっているため、テキスト代や印刷費用も不要です。
もちろん、自宅で使用する端末(PCやタブレット、ネット環境)は家庭で準備する必要がありますが、それ以外にサービス側から請求される追加費用はありません。
また、更新料やシステム維持費といった名目の料金も発生しないため、継続して学ぶ際の費用が明確で分かりやすいのも、保護者にとって安心できるポイントです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1契約につき兄弟・姉妹での利用が可能という大きな特徴があります。
つまり、受講料を1人分支払えば、同一家庭の中であれば2人目・3人目のお子さんも追加費用なしでアカウントを作成して利用することができます。
学年や学力に関係なく、それぞれが個別のIDと学習データを持って学べるため、「兄は中学1年生、弟は小4」など、学年が離れている場合でも問題ありません。
この仕組みは他の家庭学習サービスではあまり見られないもので、特に兄弟の多いご家庭にとっては非常にコスパが良く、負担を抑えながら質の高い学習を提供できるメリットがあります。
もちろん、それぞれの学習進捗や弱点分析も個別で記録されるため、混ざることなく安心して使えます。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには「英語」も用意されています。
無学年式の教材設計のため、小学1年生でも中学英語の基礎内容に触れることが可能で、早い段階から英語に親しみたい家庭にも適しています。
授業はアニメキャラクターとの対話形式で進行し、「聞く・話す・読む」の3技能をバランスよく習得できるように作られています。
とくに初学者がつまずきやすいbe動詞や一般動詞、疑問文のつくり方なども丁寧に解説されており、英語が苦手なお子さんでも安心して取り組める内容です。
また、単語の反復練習やスピーキングの練習コンテンツもあり、家庭で自然と英語学習が習慣になるよう設計されています。
フォニックスを活用した音の学習もあるため、耳からの学びにも力を入れています。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの大きな魅力のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる専属の学習サポーターの存在です。
このコーチは、子どもの学習進捗をチェックしながら、個別にアドバイスを送ってくれる存在で、学習計画の作成、進度の管理、モチベーション維持の声かけまでを担ってくれます。
保護者がすべてを管理しなくても、コーチがLINEやメールで定期的にフィードバックをくれるため、忙しいご家庭でも安心して任せることができます。
また、コーチは子どもの性格や理解度に応じて、声かけのトーンやアドバイスの内容を調整してくれる柔軟さも持っており、「わかるまで待ってくれる」「無理に進めさせない」スタイルで寄り添ってくれます。
困ったことや不安があれば保護者からも相談ができるため、二人三脚で学習を支えてくれる頼もしい存在です。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
今回は、【すらら】というタブレット教材について、料金や最悪の噂、口コミなどを比較してまとめました。
【すらら】に関する情報を正確に把握することで、お子様の学習環境を見直す際の参考になるかと存じます。
料金面では、【すらら】の月額費用やコース内容などを詳細に比較しました。
また、最悪の噂についても検証し、その信憑性を考察しました。
さらに、実際に【すらら】を利用した方々の口コミや評価をまとめ、その特徴や利点、欠点についても述べました。
この比較まとめを通じて、【すらら】に関心をお持ちの方々が、より客観的な視点で情報収集を行う一助となれば幸いです。
教育におけるタブレット教材は、お子様の学びや成長に大きな影響を与える重要な要素です。
そのため、十分な情報収集や検討を行い、お子様に最適な学習環境を整えることが大切です。
最後に、【すらら】を含むタブレット教材についてさらに詳しく知りたい方は、公式サイトや実際に利用された方々の声を参考にすることをお勧めします。
お子様の将来のために、最適な学習環境を整えるお手伝いができれば幸いです。